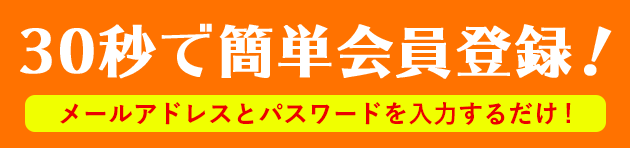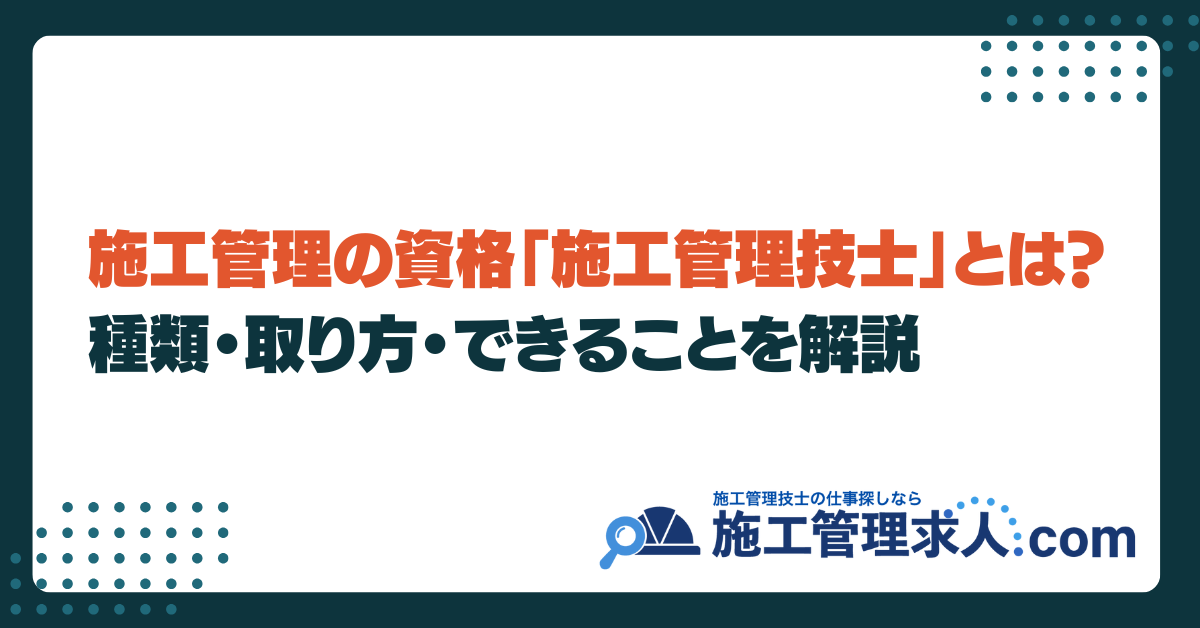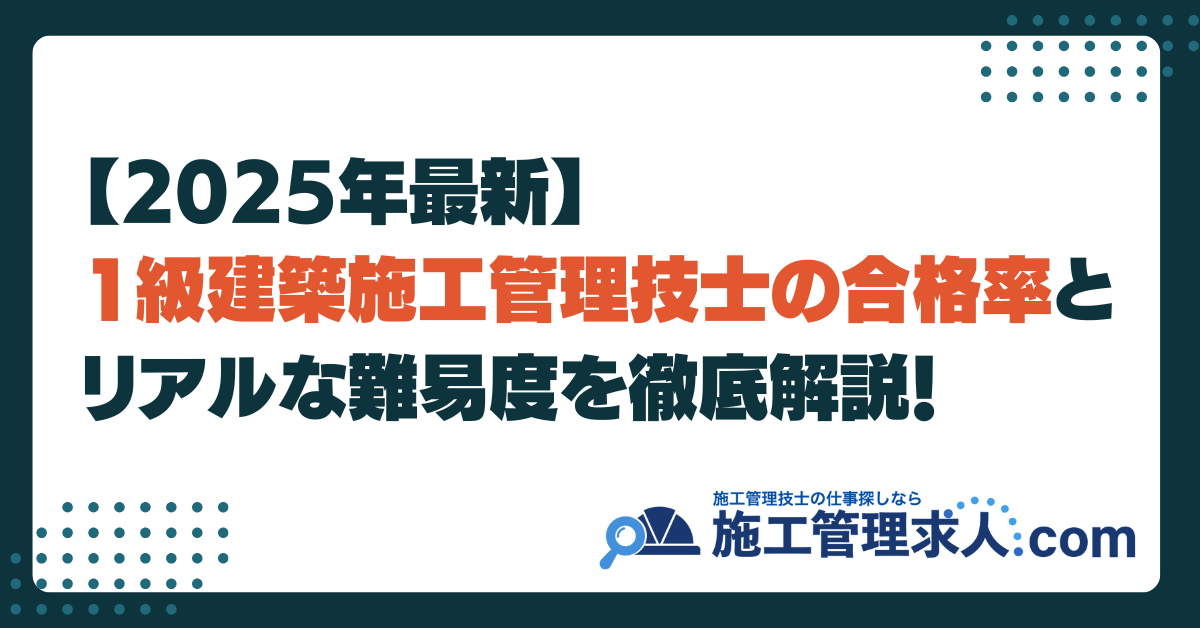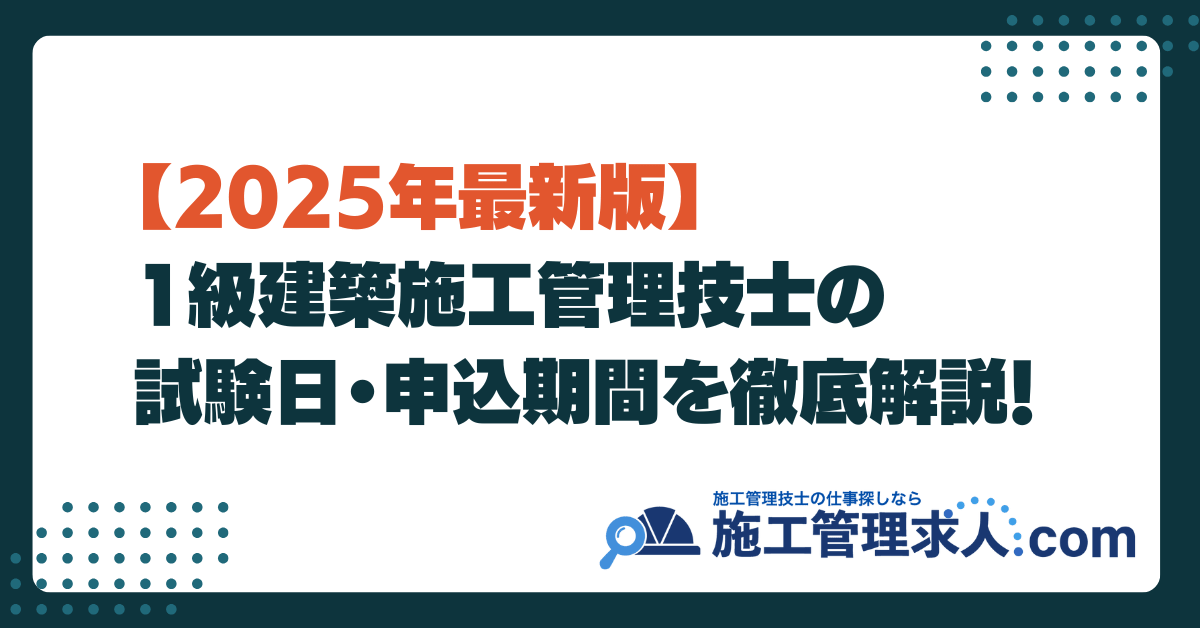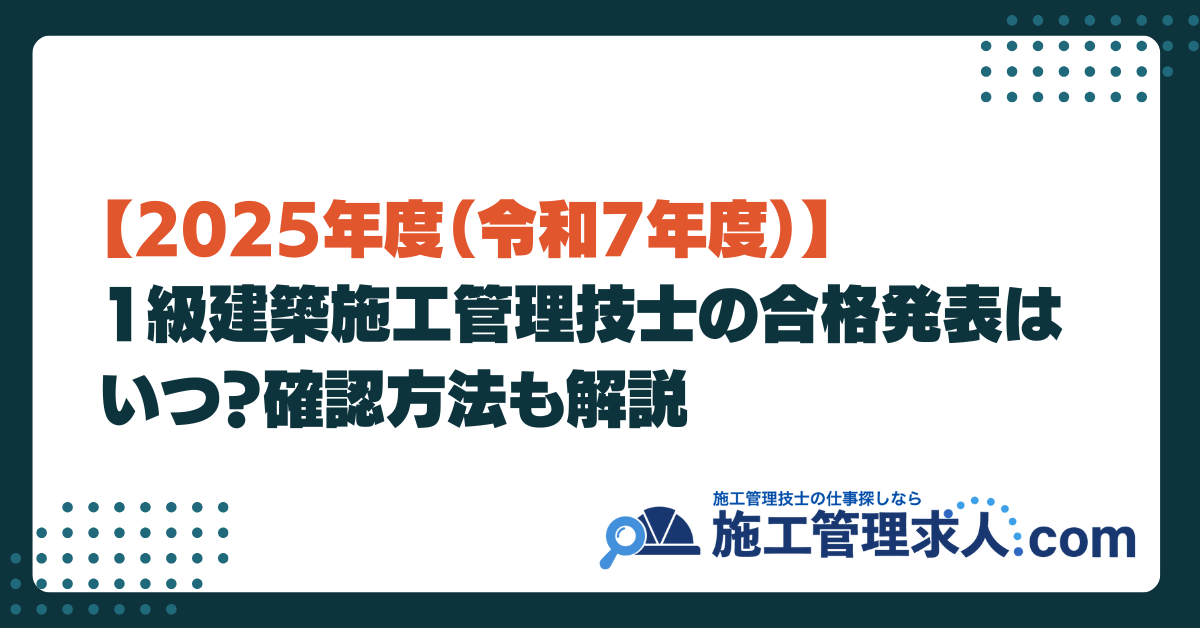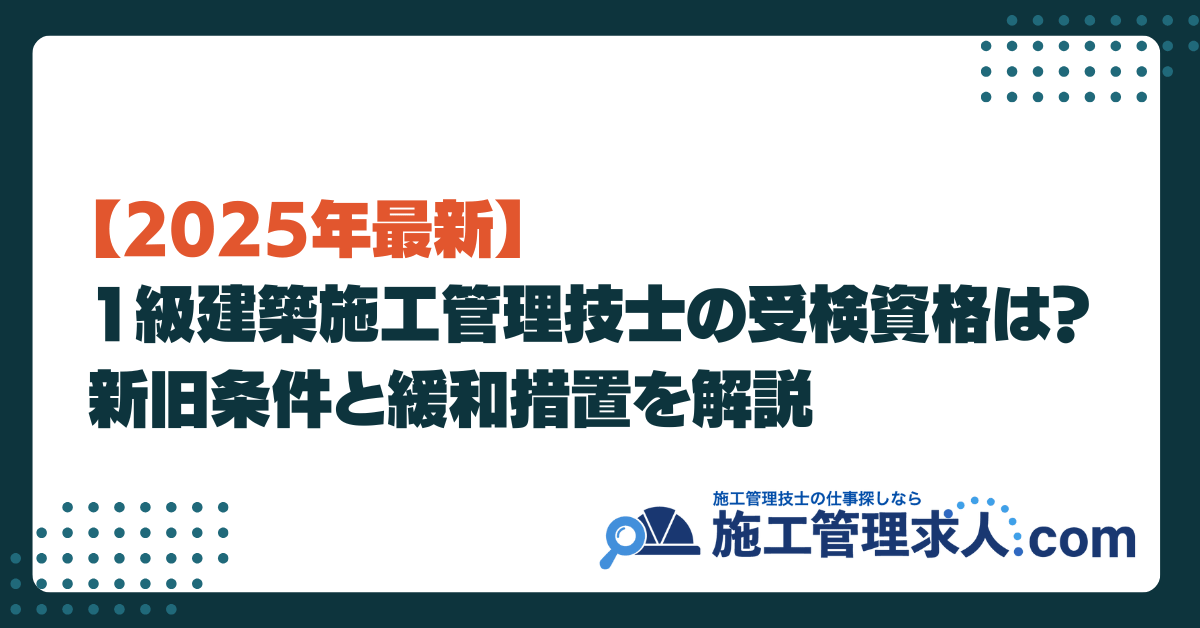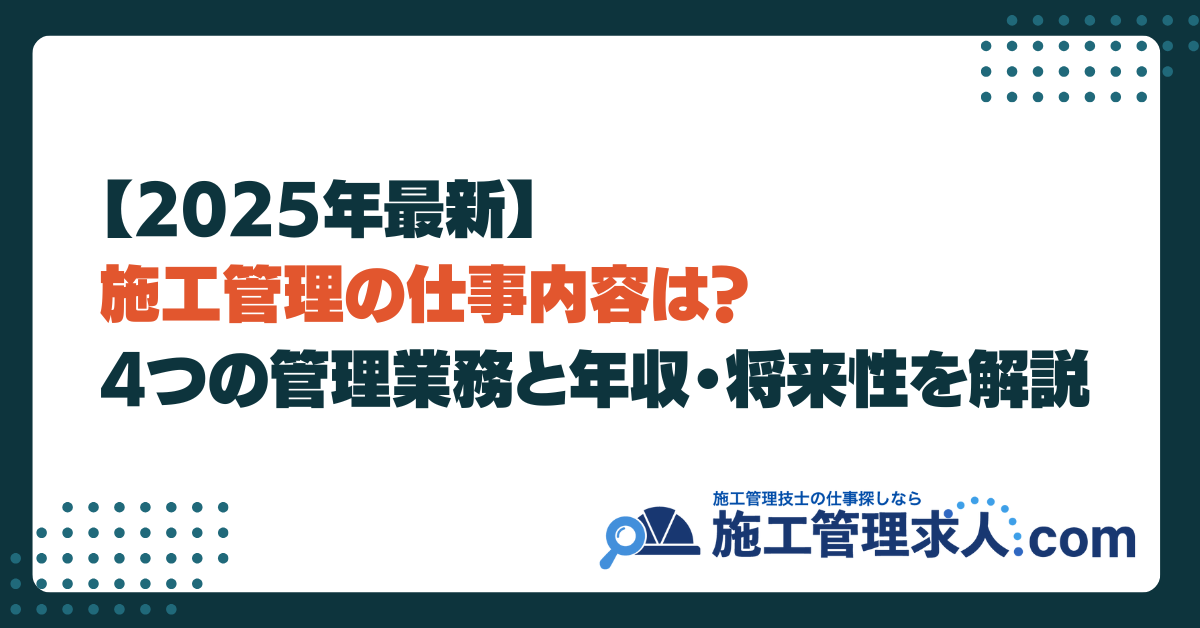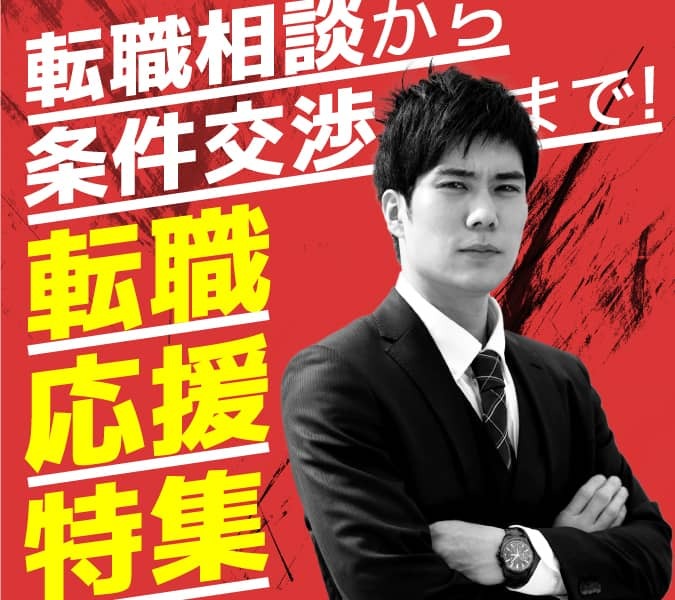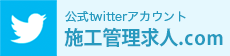- いきなり1級建築施工管理技士を受験できるかどうかの明確な答え
- 【2025年最新】1級の受験資格(令和6年度緩和対応)の詳細
- あなたの学歴や経験に応じた最短ルート
- いきなり1級を目指すメリット・デメリット
- 合格に向けた勉強法と実務経験のポイント
いきなり1級建築施工管理技士の受検は可能?受験資格・緩和措置・最短ルートを解説
最終更新日:
1級建築施工管理技士の試験は、2級を持っていない人でも「いきなり」受験可能です。 令和6年度の緩和により、第一次検定は19歳以上なら誰でも挑戦できますが、正式な「1級建築施工管理技士」になるための第二次検定には実務経験が必要です。
建設業界で活躍を目指すあなたにとって、1級建築施工管理技士の資格は大きな目標の一つでしょう。特に、受験資格が緩和されたことで、「いきなり1級建築施工管理技士を目指すこと」への関心が高まっています。
この記事では、施工管理技士専門の転職エージェント「施工管理求人.com」が、国土交通省や建設業振興基金の最新情報をもとに、いきなり1級建築施工管理技士を目指す際のさまざまな疑問に徹底的にお答えします。この記事を読めば、以下の点が明確になります。
複雑な受験資格やキャリアプランに関する不安をこの記事で解消し、自信を持って資格取得への第一歩を踏み出しましょう。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりいい職場で働く
【結論】建築施工管理技士はいきなり1級から受験可能!ただし注意点も
1級建築施工管理技士の試験は、条件を満たせば2級を経ずに「いきなり」受験することが可能です。 特に令和6年度からの受験資格緩和によって、その門戸は大きく広がりました。
しかし、いくつか重要な注意点もありますので、すぐに飛びつく前にしっかり理解しておきましょう。
令和6年度の受験資格緩和で第一次検定は19歳以上なら誰でも受験可能に
第一次検定については、令和6年度から実務経験要件が撤廃され、19歳以上であれば誰でも受験できるようになりました。 これが今回の受験資格緩和における最大のポイントです。
これにより、試験実施年度の末日時点で満19歳以上であれば、学歴や実務経験に関わらず、誰でも1級建築施工管理技士の第一次検定に挑戦できるようになりました。(出典:国土交通省、一般財団法人建設業振興基金)
これは、建設業界の人手不足解消と若手技術者の育成を目的とした大きな変更です。学生や実務経験の浅い方、異業種からの転職を考えている方にとっても、早期に1級を目指せるチャンスが生まれたと言えるでしょう。
■第一次検定 受験資格の比較
| 区分 | 緩和前(~令和5年度) | 緩和後(令和6年度~) |
|---|---|---|
| 年齢 | 特になし | 試験年度末時点で19歳以上 |
| 学歴 | 学歴に応じて必要な実務経験年数が異なる | 不問 |
| 実務経験 | 学歴に応じて必要(例:大卒指定学科3年以上) | 不要 |
旧資格については建築施工管理技士の受験資格とは?|1級・2級の技術検定について解説!で詳しく解説しています。
ただし「1級建築施工管理技士」になるには第二次検定合格と実務経験が必須
注意点として、第一次検定に合格しても、それだけでは「1級建築施工管理技士」の資格を取得したとは言えません。
第一次検定合格者は「技士補(1級建築施工管理技士補)」という資格を得られます。ただ、「技士補」は監理技術者の補佐として現場で活躍できるものの、正式な「1級建築施工管理技士」として認められていません。
正式に「1級建築施工管理技士」を取得し監理技術者などを担当するためには、さらに第二次検定(実地試験に相当)に合格する必要があります。
そして、この第二次検定を受験するためには、依然として一定の実務経験が必要となります。
※出典:一般財団法人建設業振興基金
つまり、「いきなり1級建築施工管理技士の第一次検定は受けられる」ものの、「いきなり(実務経験なしで)1級建築施工管理技士の資格を取得できる」わけではない、という点をしっかり押さえておく必要があります。
いきなり1級建築施工管理技士に挑戦する前に知っておきたい注意点
いきなり1級を目指す際には、いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。 第一次検定のハードルは下がりましたが、以下の点を考慮しましょう。
■注意点
- 試験の難易度
1級建築施工管理技士の試験は、2級と比較して格段に難易度が上がります。特に第二次検定では、実務経験に基づいた深い知識や応用力が問われるため、経験が浅い場合は不利になることも考えられます。 - 実務経験の重要性
第二次検定の受験には実務経験が必須です。第一次検定に合格しても、必要な実務経験を満たしていなければ第二次検定は受験できません。 - 基礎知識の習得
2級の学習過程を飛ばすことになるため、施工管理に関する基礎知識が不足するかもしれません。1級の学習内容を理解するためにも、基礎固めは重要です。
1級建築施工管理技士試験の難易度は決して低くありません。参考までに、令和6年度(2024年度)の第一次検定の合格率は36.2%、第二次検定の合格率は40.8%でした。
※出典:一般財団法人建設業振興基金発表データに基づく
具体的な合格率の推移や勉強法については、1級建築施工管理技士の難易度や勉強法に関する記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
最新の試験情報は必ず一般財団法人建設業振興基金 試験研修本部の公式サイトでご確認ください。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりいい職場で働く
■この見出しのポイント
いきなり1級建築施工管理技士の第一次検定に挑戦することは、19歳以上であれば可能です。
ただし、正式な「1級建築施工管理技士」になるには第二次検定の合格と実務経験が不可欠です。難易度や基礎知識の重要性も踏まえ、計画的に準備を進めましょう。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりいい職場で働く
【2025年最新】1級建築施工管理技士の受験資格を徹底解説(令和6年度緩和対応)
ここでは、令和6年度の緩和措置に対応した最新(2025年時点)の1級建築施工管理技士の受験資格を解説します。 第一次検定と第二次検定に分けて詳しく見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせながら確認してください。
第一次検定の受験資格|19歳以上なら実務経験不問!
令和6年度以降、1級建築施工管理技士の第一次検定は、19歳以上であれば学歴や実務経験を問わず受験可能です。
■第一次検定 受験資格(令和6年度以降)
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢 | 試験実施年度の末日時点で19歳以上であること |
| 学歴 | 不問 |
| 実務経験 | 不要 |
※出典:一般財団法人建設業振興基金
これにより、例えば大学在学中の学生や、建設業界に入ったばかりの方でも、早期に第一次検定に挑戦し、「技士補」の資格を取得することが可能になりました。
1級建築施工管理技士の受検資格について、より詳細な情報は【2025年最新】1級建築施工管理技士の受検資格は?新旧条件と緩和措置を解説をご参照ください。
第二次検定の受験資格|必要な実務経験年数と種類をパターン別に解説
第二次検定を受験するには、1級第一次検定合格に加え、一定の実務経験が必要です。
要件は第一次検定に比べて少し複雑になりますので、パターン別に見ていきましょう。
■第二次検定 受験要件パターン
| No. | パターン | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 1級建築施工管理技士 第一次検定合格後の実務経験 |
|
| 2 | 2級建築施工管理技士 第二次検定合格後の実務経験 (※3) |
|
| 3 | 一級建築士試験合格後の実務経験 |
|
(※1) 特定実務経験:請負金額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該技術者の指導の下で経験した場合も含む)として従事した経験。
(※2) 監理技術者補佐:1級技士補として、監理技術者を補佐する立場での実務経験。
(※3) 旧2級実地試験合格者を含み、建築・躯体・仕上げの種別は問いません。
建築施工管理技士全体の基本的な受験資格(旧資格も含む)については、建築施工管理技士の基本的な受験資格に関する記事も参考にしてください。
なお、1級建築施工管理技士の受検資格について、より詳細な情報は【2025年最新】1級建築施工管理技士の受検資格は?新旧条件と緩和措置を解説をご参照ください。
最新の技術検定制度については国土交通省のページも参照ください。
【重要】実務経験として認められる工事・認められない工事
第二次検定の受験資格で重要となる「実務経験」ですが、全ての建設関連業務が認められるわけではありません。 基本的には、建築一式工事または各種専門工事の施工に直接関わる技術上の管理業務が対象です。
■認められる業務の例
- 施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理
- 現場での技術指導、監督業務
- 資材の品質管理、検査業務
- 建設工事の請負契約に関する技術的な業務
■認められない業務の例
- 設計業務のみ(施工管理を伴わないもの)
- 積算、庶務、会計などの事務作業
- 営業職
- 単なる作業員としての業務
- 建設業の許可を受けていない業者での経験(一部例外あり)
- 海外での実務経験(原則)
実務経験を証明するためには、実務経験証明書の提出が必要です。
単に工事に携わっただけでなく、「どのような立場で」「どのような管理業務を行ったか」を具体的に記述する必要があります。
勤務先に証明してもらう必要があるため、日頃から自身の業務内容(担当工事、立場、具体的な管理内容)を記録し、証明書作成に備えておくことが重要です。
最新の試験日程・申込期間は?
1級建築施工管理技術検定は、例年、第一次検定が夏頃、第二次検定が秋頃に実施されます。参考として、2025年度(令和7年度)の試験日程(予定)は以下の通りです。
■1級建築施工管理技士 試験日程
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 申込期間(第一次検定のみ) | 令和7年2月14日(金)~4月7日(月) |
| 申込期間(第一次検定・第二次検定) | 令和7年2月14日(金)~2月28日(金) |
| 申込期間(第二次検定のみ) | 令和7年2月14日(金)~2月28日(金) |
| 第一次検定 試験日 | 令和7年7月20日(日) |
| 第一次検定 合格発表日 | 令和7年8月22日(金) |
| 第二次検定 試験日 | 令和7年10月19日(日) |
| 第二次検定 合格発表日 | 令和8年1月9日(金) |
最新の情報は必ず一般財団法人建設業振興基金 試験研修本部の公式サイトでご確認ください。
最新の試験日程や申込方法の詳細については、【2025年度版】1級建築施工管理技士 試験日・申込期間に関する記事で詳しく解説しています。
■この見出しのポイント
第一次検定は19歳以上であれば受験できますが、第二次検定には第一次検定合格と一定の実務経験が求められます。どのような業務が実務経験として認められるのか、しっかり確認しておきましょう。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりいい職場で働く
あなたはどのルート?学歴・経験別「いきなり1級」最短攻略法
※ここでは、令和6年度以降の新受験資格制度を前提とした最短ルートを解説します。
ご自身の学歴や実務経験によって、いきなり1級を目指すための最適なルートは異なります。 ここでは代表的なケース別に、最短攻略法を解説します。
ケース1:建築系大学卒・実務経験ありの場合
建築系の大学(指定学科)卒で実務経験がある方は、第一次検定合格後、必要な実務経験(最短ルートは監理技術者補佐1年など。詳細は前項参照)を満たせば第二次検定へ進めます。
■ルート
第一次検定合格
→ 必要な実務経験(監理技術者補佐1年/特定実務経験含む3年/一般5年など)
→ 第二次検定受験
■ポイント
第一次検定はいつでも挑戦可能。実務経験年数を満たすタイミングで第二次検定へ。
ケース2:建築系大学卒・実務経験なし(または浅い)の場合
建築系の大学(指定学科)卒で実務経験がない(または浅い)方は、まず第一次検定に合格し「技士補」となり、その後実務経験を積むルートが基本です。
■ルート
第一次検定合格(技士補取得)
→ 必要な実務経験を積む
→ 第二次検定受験
■ポイント
技士補として働きながら実務経験を積み、第二次検定を目指します。
ケース3:高校卒・実務経験ありの場合
高校(指定学科)卒で実務経験が豊富な方は、第一次検定合格後、必要な実務経験(最短ルートは監理技術者補佐1年など。詳細は前項参照)を満たせば第二次検定へ進めます。
■ルート
第一次検定合格
→ 必要な実務経験(監理技術者補佐1年/特定実務経験含む3年/一般5年など。)
→ 第二次検定受験
■ポイント
第一次検定はいつでも挑戦可能。これまでの実務経験が第二次検定の要件を満たしていれば、スムーズに進めます。(旧資格での受験も要検討)
ケース4:未経験・異業種からの挑戦の場合
未経験・異業種から挑戦する場合は、まず第一次検定合格を目指し、同時に実務経験を積む環境を見つけることがスタートラインです。
■ルート
第一次検定合格を目指す + 実務経験を積める会社へ就職/転職
→ 必要な実務経験(最短は監理技術者補佐1年など)
→
第二次検定受験
■ポイント
第一次検定の勉強と並行して、実務経験を積める環境探しが重要です。育成体制の整った企業を選びましょう。
ケース5:2級建築施工管理技士 保有者の場合
2級建築施工管理技士(第二次検定合格者)は、1級第一次検定に合格すれば、2級合格後の実務経験に応じて第二次検定を受験できます。
■ルート
1級第一次検定合格
→ 2級第二次検定合格後の実務経験(特定実務経験含む3年/一般5年など)
→ 第二次検定受験
■ポイント
1級第一次検定の合格は必須です。2級合格後の実務経験が活かせます。
※実務経験が非常に長い方は、旧受験資格でのルートが有利な場合もあります。ご自身の状況に合わせて建設業振興基金の情報を必ずご確認ください。
■この見出しのポイント
ご自身の学歴や実務経験によって、1級への最短ルートは異なります。まずは第一次検定合格を目指しつつ、第二次検定に必要な実務経験をどう積むか計画することが大切です。特に未経験の方は、実務経験を積める環境選びが最初の重要なステップとなるでしょう。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりいい職場で働く
いきなり1級を目指すメリット・デメリット|2級取得と比較
いきなり1級を目指すか、まずは2級からステップアップするかは、重要な選択です。 それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身に合った道を選びましょう。
メリット|時間短縮、早期キャリアアップの可能性
いきなり1級を目指す最大のメリットは、資格取得までの時間短縮と早期のキャリアアップが期待できる点です。
■メリット
2級の受験勉強や試験、合格発表までの期間を省略できます。最短で1級技士補、そして1級技士へと進むことができれば、キャリアアップのスピードが早まります。
早く1級を取得できれば、監理技術者として大規模プロジェクトに携わるチャンスや、昇進・昇給の機会も早く訪れる可能性があります。資格手当なども早くから得られるかもしれません。
一般的に、1級建築施工管理技士の平均年収は、2級保有者や資格なしの場合と比較して高い傾向にあります。求人情報サイトなどの調査では500万円後半から600万円以上、経験や役職によってはさらに高額になるケースも見られ、早期の1級取得は生涯年収にも良い影響を与えるでしょう。
デメリット|難易度の高さ、実務経験不足のリスク
一方で、いきなり1級を目指すことには、試験の難易度の高さや実務経験不足によるリスクも伴います。
■デメリット
1級試験は2級に比べて出題範囲が広く、求められる知識レベルも格段に上がります。特に第二次検定の経験記述問題は、実務経験が浅いと対応に苦労する可能性があります。
第一次検定に合格しても、第二次検定に必要な実務経験が不足していれば、結局「技士補」のまま足踏みすることになります。また、経験不足のまま難易度の高い1級の学習を進めると、理解が追いつかず挫折しやすいリスクも考えられます。
2級で学ぶべき基礎的な知識を飛ばしてしまうことで、応用力が身につきにくくなる可能性があります。
1級と2級の具体的な難易度の違いについては、1級と2級の難易度の違いに関する記事もご参照ください。(参考:令和6年度合格率 1級一次36.1%/二次40.8%)
2級を取得する意義は?緩和後の位置づけ
受験資格が緩和された現在でも、2級建築施工管理技士の資格を取得することには意義があります。
■2級建築施工管理技士を取得するメリット
- 主任技術者の要件
建設業法上、多くの工事現場で必要とされる「主任技術者」になるためには、2級以上の資格が必要です。1級を目指す過程でも、まず主任技術者として経験を積むことは重要です。 - 基礎固め
2級の学習内容は1級の基礎となります。段階的に学習を進めることで、知識を確実に定着させやすくなります。 - 実務経験の証明
2級を取得していることは、一定レベルの知識と実務経験があることの証明となり、転職時などに有利に働く場合があります。 - 自信と達成感
まず2級に合格することで、自信と達成感を得られ、1級へのモチベーションに繋がるでしょう。
いきなり1級を目指す場合でも、2級レベルの知識習得は不可欠です。どちらのルートを選ぶかは、ご自身の学習スタイル、実務経験の状況、キャリアプランなどを総合的に考慮して判断しましょう。
■この見出しのポイント
いきなり1級を目指すルートは時間的なメリットがある一方、試験の難易度や実務経験不足のリスクも考慮しなければなりません。2級取得には基礎固めや転職でのアピールといった利点もあります。ご自身の状況や目標に合わせて、どちらの道が最適か慎重に検討しましょう。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりいい職場で働く
いきなり1級合格を掴む!勉強法と実務経験の積み方
いきなり1級建築施工管理技士の合格を目指すためには、効率的な学習と質の高い実務経験が不可欠です。 ここでは、合格をより確実にするためのポイントをご紹介します。
効率的な学習計画の立て方と勉強法
1級試験は出題範囲が広いため、合格には計画的な学習が欠かせません。 以下の点を意識して学習を進めましょう。
■第一次・第二次検定対策
第一次検定は過去問演習を中心に、知識のインプットとアウトプットを繰り返すことが重要です。第二次検定は、経験記述対策が鍵となります。自身の経験を整理し、採点者に伝わるように記述する練習が必要です。施工管理法に関する応用問題対策も欠かせません。
■過去問の徹底活用
過去数年分の過去問題を繰り返し解き、出題傾向を掴みましょう。間違えた箇所は、なぜ間違えたのかを徹底的に理解することが重要です。
■独学 vs 講座利用
独学は費用を抑えられますが、学習効率やモチベーション維持が課題となりがちです。特に経験記述対策は独学では難しい面もあるでしょう。資格学校や通信講座は費用がかかりますが、効率的なカリキュラムやプロの指導、添削サポートを受けられるメリットがあります。ご自身の状況に合わせて検討しましょう。
■スキマ時間の活用
通勤時間や休憩時間などを活用し、アプリや単語帳などで少しずつでも知識を積み重ねることが大切です。
■モチベーション維持
学習仲間を見つけたり、定期的に模試を受けたりして、モチベーションを維持する工夫をしましょう。合格後のキャリアアップを具体的にイメージすることも有効です。
具体的な勉強時間やおすすめの参考書など、学習方法の詳細は1級建築施工管理技士の勉強法 詳細に関する記事で詳しく解説しています。
第二次検定を見据えた実務経験の積み方
第二次検定の経験記述対策として、日々の業務で「質の高い」実務経験を意識的に積むことが重要です。
■経験記述を意識する
日々の業務の中で、「これは経験記述に書けるかもしれない」という視点を持ちましょう。特に、工程管理(遅延対策など)、品質管理(不具合防止策など)、安全管理(事故防止策など)、環境管理(騒音・振動対策など)で、自身が主体的に関与し、工夫した点、課題を解決した経験などを具体的に記録しておくと、第二次検定の記述問題で非常に役立ちます。
■多様な経験を積む
可能であれば、異なる種類の工事(新築、改修、木造、RC造、S造など)や、異なる立場(現場代理人補佐、工程担当、安全担当など)を経験することで、記述の引き出しが増え、対応力が向上します。
■実務経験証明書を意識する
どのような業務が実務経験として認められるかを理解し、日々の業務記録(工事名、工期、請負金額、自身の立場、具体的な管理業務内容など)を詳細に残しておきましょう。これが後の実務経験証明書の作成に不可欠です。
実務経験が積める会社選びのポイント
特に未経験から挑戦する場合や、現在の職場で十分な実務経験が積めないと感じる場合は、転職も有効な選択肢です。 実務経験を積みやすく、資格取得を後押ししてくれる会社を選ぶ際のポイントを紹介します。
■資格取得支援制度
受験費用や講座費用の補助、資格手当、合格祝い金などの制度があるか。
■工事実績
1級の受験資格となる規模の工事(特定建設業の許可があるかなど)や、多様な種類の工事実績があるか。
■育成体制
未経験者や若手に対するOJT(On-the-Job Training)や研修制度が充実しているか。
■資格保有者の存在
社内に1級建築施工管理技士が多く在籍し、指導やアドバイスを受けやすい環境か。
■働き方
残業時間や休日数など、学習時間を確保しやすい労働環境か。
■【実務経験が積める会社選び チェックリスト】
- □ 資格取得支援制度(費用補助、手当など)があるか?
- □ 1級の受験資格に必要な規模の工事実績があるか?(特定建設業許可など)
- □ 多様な工事種類(新築、改修、RC造、S造など)を経験できるか?
- □ 未経験者や若手向けの研修・OJT制度が整っているか?
- □ 社内に1級資格保有者が多く、指導を受けやすい環境か?
- □ 学習時間を確保しやすい労働環境(残業時間、休日数)か?
- □ 実務経験証明書の発行に協力的か?
実務経験が積める企業を探すなら、施工管理技士専門の求人サイト「施工管理求人.com」をご活用ください。あなたの希望に合った企業探しをサポートします。(無料でキャリア相談する)
■この見出しのポイント
いきなり1級合格を目指すなら、計画的な学習と質の高い実務経験の両方が欠かせません。過去問演習や必要に応じた講座活用で効率的に学習を進め、第二次検定の経験記述を意識しながら日々の実務経験を積み重ねることが重要です。また、資格取得をサポートしてくれる会社を選ぶことも、合格への近道となるでしょう。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりいい職場で働く
よくある質問(FAQ)
Q1. 施工管理技士1級になるには最短で何年必要ですか?
選択するルートによって異なります。 令和6年度以降の制度では、1級第一次検定合格後、監理技術者補佐としての実務経験を1年積むのが、第二次検定受験資格を得る最短ルートの一つです。ただし、第一次検定合格前に実務経験を積む期間が必要になることもあります。ご自身の学歴や状況によって最適なルートは変わるため、本文のケース別解説や建設業振興基金の公式情報を確認してください。
Q2. 建設業で一番難しい資格は何ですか?
一概に「一番」を決めるのは難しいですが、一般的に建築士(特に一級建築士)や技術士(建設部門)などが最難関資格として挙げられます。 1級建築施工管理技士も合格率は決して高くなく、実務経験も求められるため、難関資格の一つと言えるでしょう。
Q3. いきなり1級管工事(または電気工事など他の種別)も受けられますか?
はい、第一次検定については可能です。 令和6年度からの受験資格緩和は、建築施工管理技士だけでなく、土木、電気工事、管工事など他の施工管理技士検定にも適用されています。したがって、他の種別でも第一次検定は19歳以上であれば実務経験不問で受験可能です。ただし、第二次検定の要件は種別ごとに異なる場合があるため、各種別の試験実施機関の情報をご確認ください。
Q4. 1級建築施工管理技士は難しいですか?
はい、難関資格の一つと言えます。 令和6年度の合格率は第一次検定が36.1%、第二次検定が40.8%でした。広範な知識に加え、第二次検定では実務経験に基づく応用力や記述力が求められます。十分な学習時間と質の高い実務経験が必要です。詳しくは1級建築施工管理技士の難易度や勉強法に関する記事もご覧ください。
Q5. 1級建築施工管理技士は「すごい」資格なのですか?
はい、建設業界において非常に価値が高く評価される資格です。 大規模工事の監理技術者になれる国家資格であり、取得には専門知識と実務経験の両方が必要とされるため、保有者は高いスキルを持つ技術者として認められます。年収アップやキャリアアップにも直結しやすく、「すごい」資格と言えるでしょう。
Q6. 1級建築施工管理技士の勉強時間はどのくらい必要ですか?
合格に必要な勉強時間は個人差が大きいですが、一般的には第一次検定で200~300時間、第二次検定で100~200時間程度が一つの目安です。 働きながら学習する場合は、半年~1年程度の計画的な学習期間を確保することが推奨されます。詳細は1級建築施工管理技士の勉強法 詳細に関する記事をご覧ください。
Q7. 1級建築施工管理技士にストレートで合格する人はいますか?
はい、第一次検定・第二次検定ともに1回で合格する、いわゆるストレート合格者もいます。
しかし、合格率は決して高くないため、誰もが簡単にストレート合格できるわけではありません。十分な準備と努力が必要です。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりいい職場で働く
まとめ|計画的に1級建築施工管理技士を目指そう
この記事では、1級建築施工管理技士にいきなり挑戦できるのか、そのための最新の受験資格(令和6年度緩和措置対応)、ルート、メリット・デメリット、そして合格に向けたポイントを解説してきました。
■要点の再確認
- いきなり1級受験は可能:
第一次検定は19歳以上なら誰でも受験できます。 - 第二次検定には実務経験が必要:
正式な技士資格取得には、一次合格後に一定の実務経験が必要です。 - 最新の受験資格を理解する:
緩和措置の内容と、ご自身の状況に合わせたルートを確認しましょう。 - メリット・デメリットを考慮:
時間効率と難易度・リスクを天秤にかけ、最適な戦略を選びましょう。 - 計画的な準備が不可欠:
合格には、効率的な学習と質の高い実務経験の両方が重要です。
受験資格が緩和され、1級建築施工管理技士への道は以前よりも開かれました。しかし、その価値や難易度が下がったわけではありません。むしろ、計画性と戦略性がより重要になったと言えるでしょう。
ご自身の学歴、実務経験、キャリアプランをしっかり見据え、最適なルートを選択し、着実にステップアップしていくことが成功への鍵となるでしょう。
「自分の場合はどのルートが最適?」
「実務経験を積める会社に転職したい」
「資格取得後のキャリアについて相談したい」
そんなあなたの疑問や不安に、施工管理技士専門のキャリアアドバイザーがお応えします。
施工管理求人.comの無料会員登録で、あなたの状況に合わせたキャリアプランニングや求人探しを始めませんか?資格取得から転職まで、私たちが全力でサポートします。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりいい職場で働く
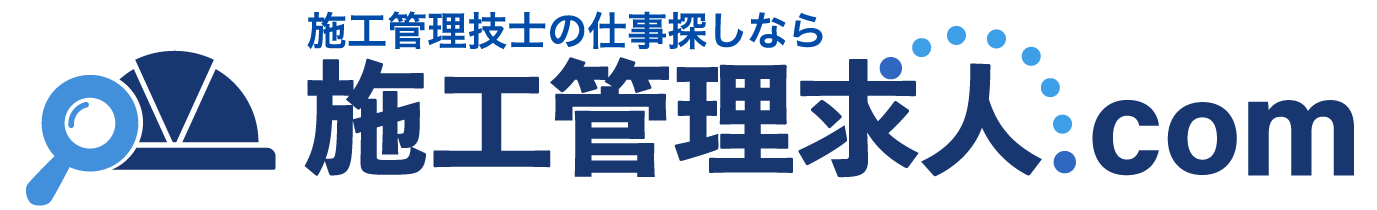
 閲覧履歴
閲覧履歴 気になる
気になる ログイン
ログイン