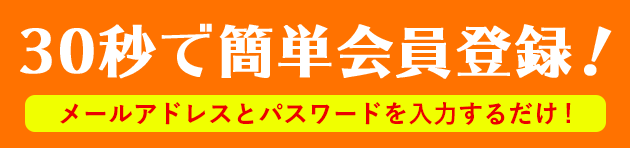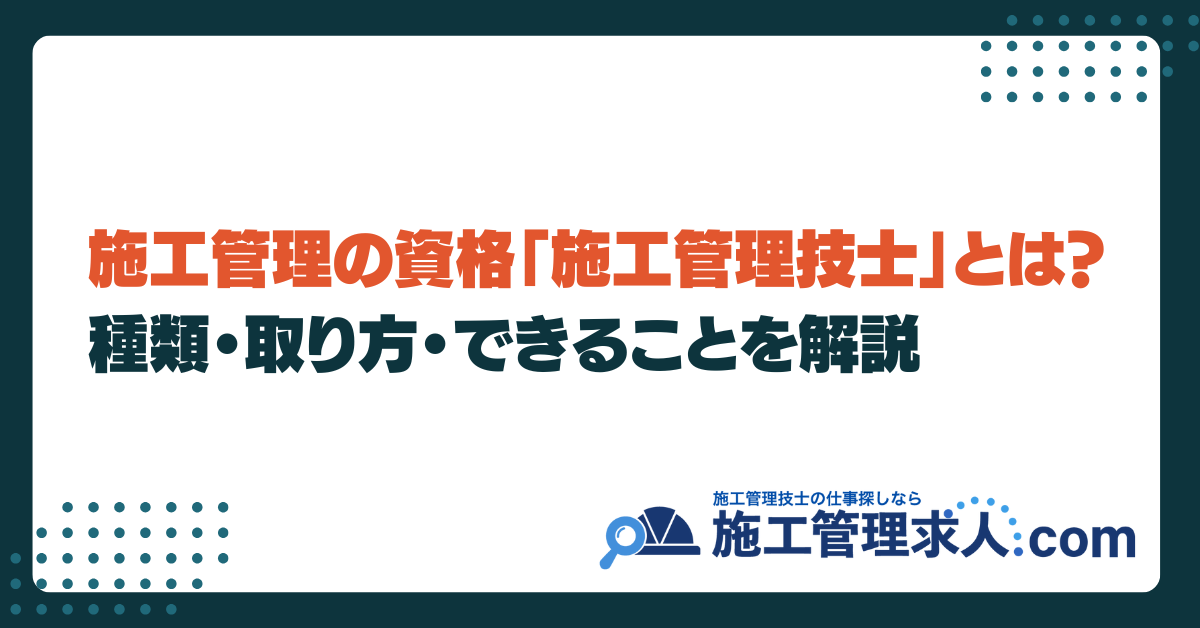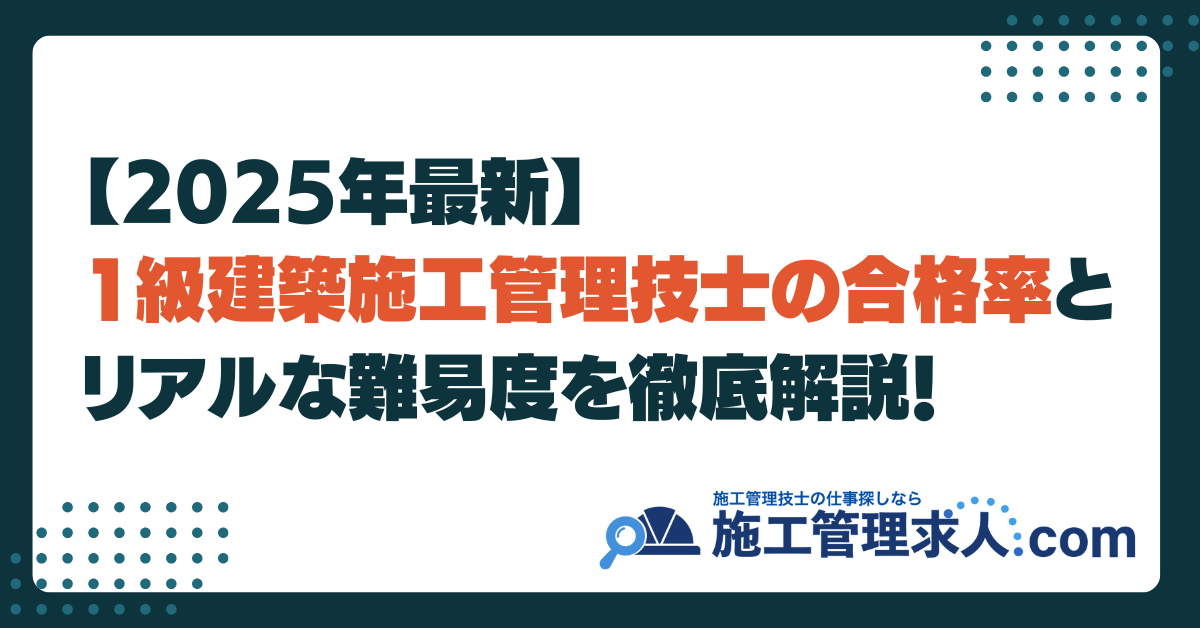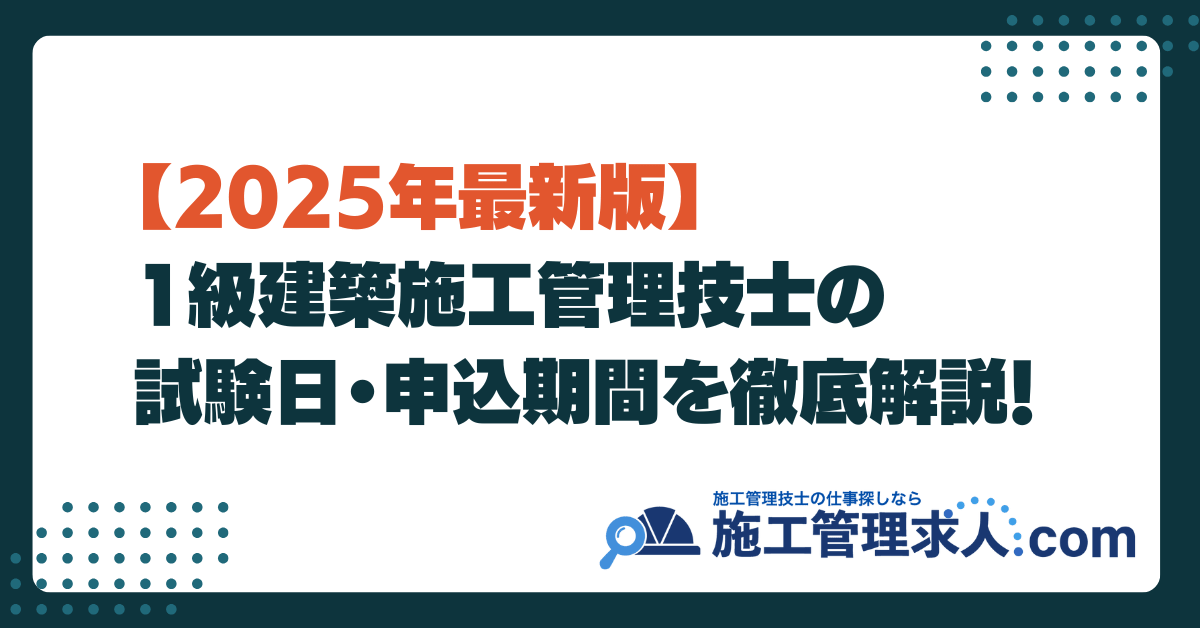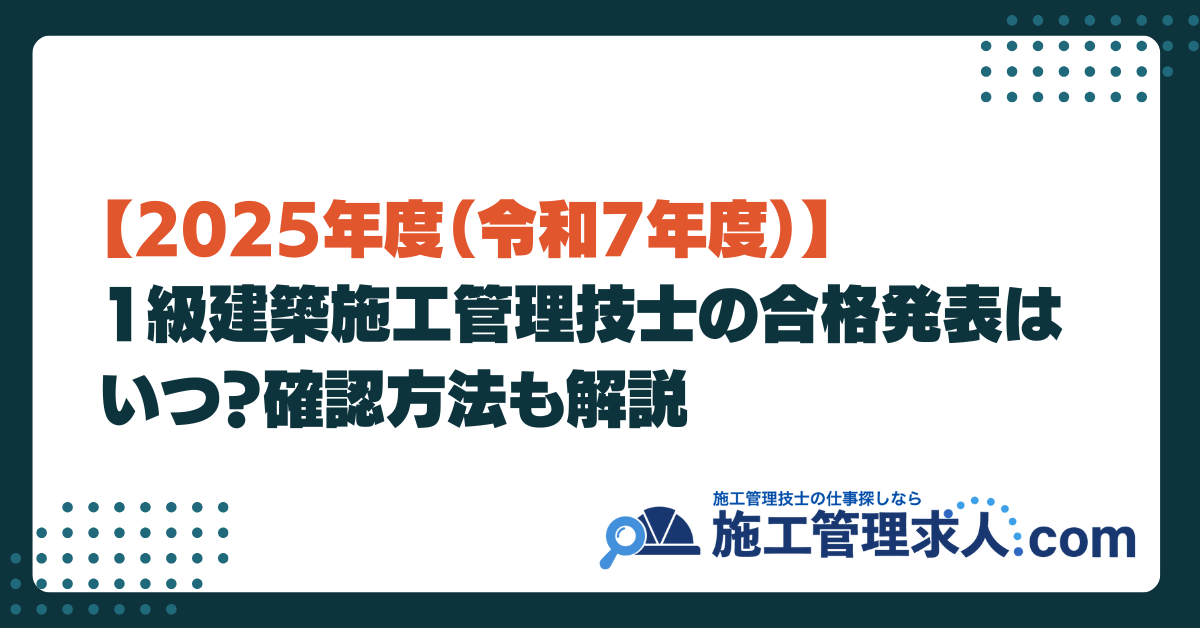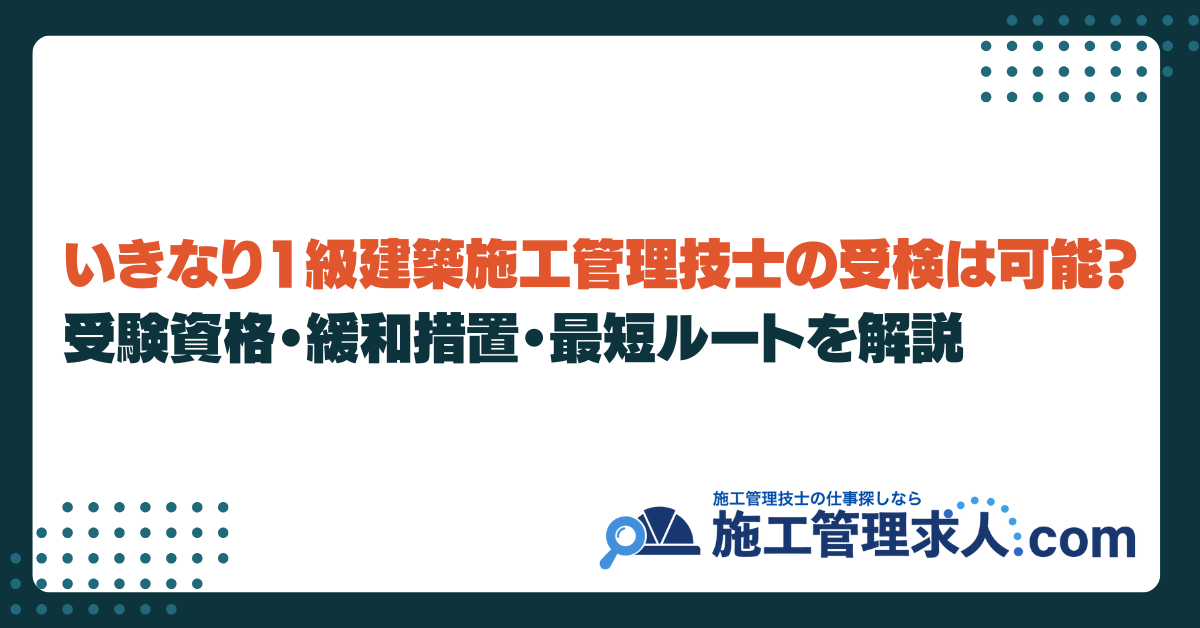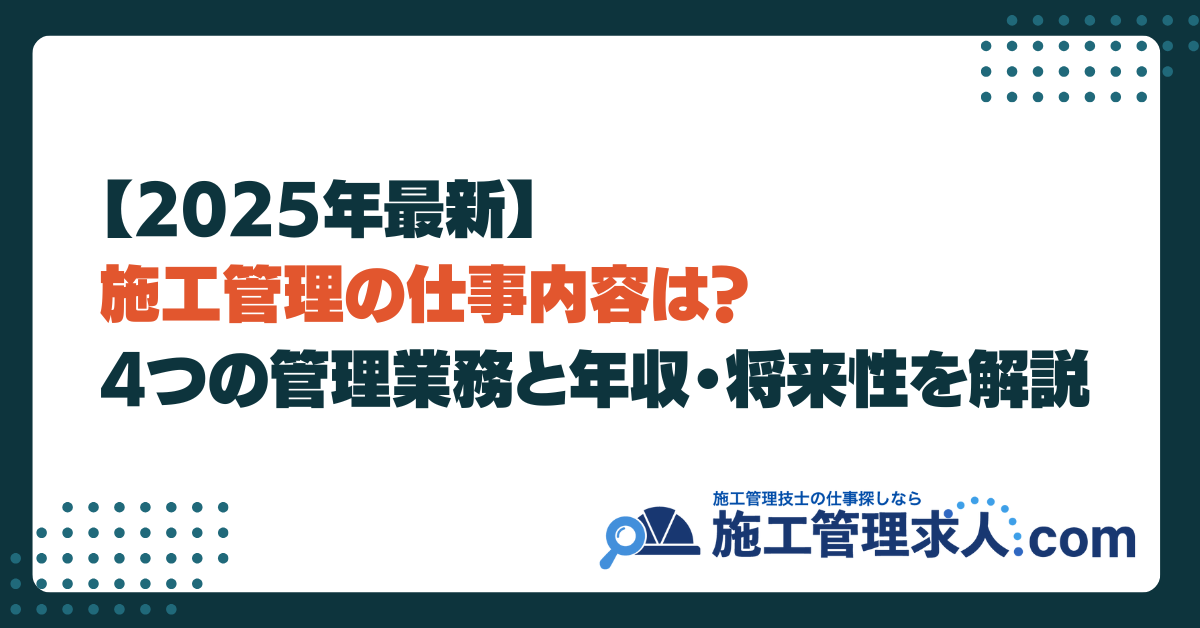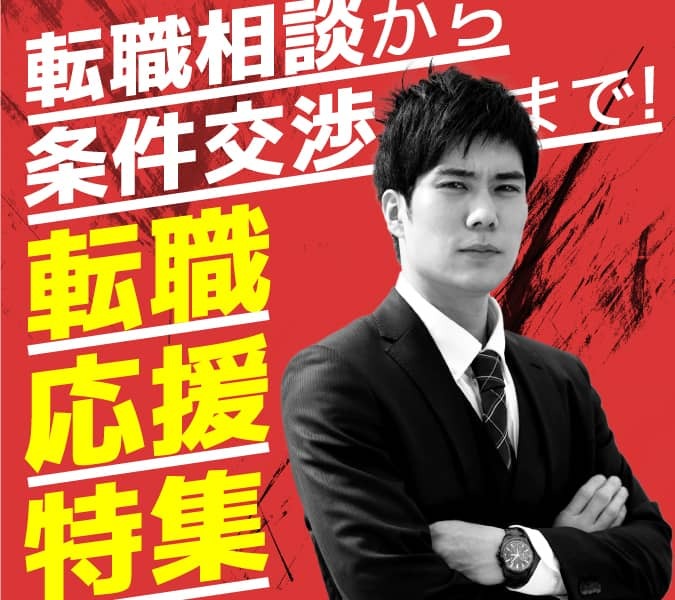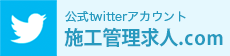施工管理技士補とは?取得のメリットや試験概要・合格率・取得方法を徹底解説!
最終更新日:
施工管理技士補は、施工管理技士の補佐的な役割を担う国家資格です。
施工管理技士の補助業務を行うことで、施工管理の実務経験を積むことができるというメリットがあります。
特に1級施工管理技士補は、「監理技術者(1級施工管理技士)」に複数現場(2つまで)を兼任させるために必要となる、「監理技術者補佐」を担当することができます。
本記事では、施工管理技士補の資格概要や取得方法、さらには新設の背景とそのメリットについて詳しく解説します。
これから施工管理職として働きたいと考えている方は、参考にしてください。
\ 完全無料で内定までサポート /
※メールアドレスのみで登録できます
■関連記事
施工管理の資格「施工管理技士」が必要な理由・種類・種類別の役割・各資格の難易度ランキングについては、「施工管理の資格「施工管理技士」とは?種類・取り方・できることを解説」で詳しく解説しています。
施工管理技士補とは?資格の概要を解説
施工管理技士補とは、施工管理技士の補佐的な役割を担う国家資格です。
ここでは、施工管理技士補の種類とできること、取得方法、新設された理由を解説します。
施工管理技士補の種類とできること
施工管理技士補には、「1級施工管理技士補」と「2級施工管理技士補」の2種類があります。
全ての施工管理技士資格(建築、電気工事、土木、管工事、電気通信工事、造園、建設機械)に対し、「1級施工管理技士補」と「2級施工管理技士補」が新設されています。
1級・2級施工管理技士補ができることは以下の通りです。
■1級・2級施工管理技士補ができること
| 資格名 | できること |
|---|---|
| 1級施工管理技士補 | 「監理技術者補佐」を担当できる |
| 2級施工管理技士補 | 法的にできることは無し・施工管理技士の補助業務 |
■監理技術者補佐とは?
監理技術者補佐とは、監理技術者を補佐する立場の技術者のことです。
監理技術者補佐を現場に配置することで、監理技術者が複数の現場を兼任することができます。
施工管理技士補を取得する方法
1級・2級施工管理技士補を取得するには、1級・2級それぞれの施工管理技術検定で一次試験に合格し、現住所(都道府県)を管轄する国土交通省各地方整備局に合格証明書の交付申請をする必要があります。
■例
1級施工管理技士の第一次検定に合格
→1級施工管理技士補の交付申請
2級施工管理技士の第一次検定に合格
→2級施工管理技士補の交付申請
合格通知書内に記載してある申請方法をよく読み、所定の申請先に申請しましょう。
施工管理技士補が新設された理由
施工管理技士補が新設された理由は、建設業界の人手不足を解消することです。
特に問題となっている、「監理技術者不足」を解消することを一番の目的として新設されました。
■ポイント
「建設業法第26条および第26条の2」では、「特定建設業者が、合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結した建設工事を行う場合は、「監理技術者」を置かなければならない」と定められています。
実務経験が必要で難易度の高い1級施工管理技士を保有している必要があることや、建設業全体の労働者減少により、現在は「監理技術者」の数が不足しています。
この対応策として制度が変更され、「1級施工管理技士補」を「監理技術者補佐」として現場に配置することで、「監理技術者」が複数現場(2つまで)を兼任できるようになりました。
これにより、法律上必要となる監理技術者の総数を削減することが可能になりました。
上記に加えて、「第一次試験(旧:学科試験)合格により施工管理技士補(国家資格)が取得できる」という制度にすることで、若手人材が施工管理技術検定に挑戦しやすい環境を作ることも目的としています。
施工管理技士補の新設は、新・担い手3法という法律の改正に含まれている内容です。
■新・担い手3法とは?
建設業の担い手の中長期的な育成・確保を目的として、令和元年に国会で可決されたのが「新・担い手3法」です。「新・担い手3法」は、建設業に関係する3つの法律の改正法をまとめた呼び方です。
- 公共工事品質確保促進法(品確法)
- 建設業法
- 公共工事入札契約適正化法(入契法)
以上3つの法改正により、建設業の「働き方改革」「生産性の向上」「調査・設計の品質確保」「持続可能な事業環境の確保」の推進を目指しています。
※参考:国土交通省「新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について」
\ 完全無料で内定までサポート /
※メールアドレスのみで登録できます
施工管理技士補新設による変更点
施工管理技士補新設による変更点は以下の通りです。
学科試験が第一次検定に、実地試験が第二次検定に名称変更
施工管理技士補新設に合わせて、従来の学科試験が「第一次検定」に、実地試験が「第二次検定」に名称が変更されました。
■学科試験・実地試験の名称変更
| 変更後 | 変更前 | |
|---|---|---|
| 変更内容 | 第一次検定 | 学科試験 |
| 第二次検定 | 実地試験 |
「監理技術者補佐」という役割が新設
施工管理技士補新設により、1級施工管理技士補が担当できる「監理技術者補佐」という役割が新設されました。
■ポイント
「監理技術者補佐」は、「建設業法第26条および第26条の2」で「特定建設業者が合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結した建設工事を行う場合に設置しなければならない」と定められている、「監理技術者」の補助を行うことができます。
これにより、監理技術者補佐を専任で設置することで監理技術者は複数現場(2つまで)を兼任できるようになりました。
■監理技術者の配置方法の変更
| 変更後 | 変更前 | |
|---|---|---|
| 変更内容 | 監理技術者補佐を専任で配置すれば、監理技術者は複数現場(2つまで)を兼任できる | 監理技術者が担当できる現場は1つまで(専任) |
上記により、必要となる監理技術者の数が削減されるため、人手不足を解消することができます。
試験問題の見直し
施工管理技士補の新設により、試験問題が見直されました。
■一級施工管理技士の試験内容
| 1級施工管理技士 | 変更後 | 変更前 |
|---|---|---|
| 第一次検定 (旧:学科試験) |
|
|
| 第二次検定 (旧:実地試験) |
|
|
■二級施工管理技士の試験問題
| 2級施工管理技士 | 変更後 | 変更前 |
|---|---|---|
| 第一次検定 (旧:学科試験) |
|
|
| 第二次検定 (旧:実地試験) |
|
|
受験資格の見直し
令和3年度の施工管理技士補の新設により、受験資格が見直され、2級施工管理技士の第二次検定に合格した人が1級施工管理技士の第一次検定に受験する場合、1級施工管理技士の受験に必要となる実務経験が不要になりました。
ただ、令和6年度の改正により、受験資格が大幅に見直され、1級施工管理技士の第一次検定の受験資格は「年齢のみ(受験年度末時点で19歳以上)」に変更されたため、上記の受験資格は削除されています。
令和6年度から令和10年度の間、第二次検定は「旧受験資格」と「新受験資格」のどちらかを選択して受験することが可能です。
■1級施工管理技士の受験資格の見直し
| 学歴等 | 新受験資格 | 旧受験資格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一次検定 | 第二次検定 | 第一次検定 | 第二次検定 | |
| 大学(指定学科) | 19歳以上 (受験年度末時点) |
■1級第一次検定合格後
|
卒業後 実務経験3年 | |
| 短大、高専(指定学科) | 卒業後 実務経験5年 | |||
| 高等学校(指定学科) | 卒業後 実務経験10年 | |||
| 大学 | 卒業後 実務経験4.5年 | |||
| 短大、高専 | 卒業後 実務経験7.5年 | |||
| 高等学校 | 卒業後 実務経験11.5年 | |||
| 2級合格者 | 条件なし | 2級合格後5年実務 ※1級第一次検定合格者のみ |
||
| 上記以外 | 実務経験15年 | |||
1級建築施工管理技士の新旧受検資格と緩和措置について詳しくは、【2025年最新】1級建築施工管理技士の受検資格は?新旧条件と緩和措置を解説で詳しく解説しています。
■2級施工管理技士の受験資格の見直し
| 学歴等 | 新受験資格 | 旧受験資格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一次検定 | 第二次検定 | 第一次検定 | 第二次検定 | |
| 大学(指定学科) | 17歳以上 (受験年度末時点) |
■2級第一次検定合格後
|
17歳以上 (受験年度末時点) |
卒業後 実務経験1年 |
| 短大、高専(指定学科) | 卒業後 実務経験2年 | |||
| 高等学校(指定学科) | 卒業後 実務経験3年 | |||
| 大学 | 卒業後 実務経験1.5年 | |||
| 短大、高専 | 卒業後 実務経験3年 | |||
| 高等学校 | 卒業後 実務経験4.5年 | |||
| 上記以外 | 実務経験8年 | |||
※参考:令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります(国土交通省)
第一次検定の合格有効期限が無期限に変更
施工管理技士補の新設により、第一次検定の合格有効期限が無期限に変更されました。
■第一次検定の合格有効期限
| 変更後 | 変更前 | |
|---|---|---|
| 第一次検定の合格有効期限 | 無期限 | 翌年度まで (翌々年度は学科から受験する必要あり) |
以前までは、第一次検定(旧:学科試験)に合格して第二次検定に合格できなかった場合、翌年度までしか第一次検定の合格を引き継げませんでした。
しかし、施工管理技士補が新設されたことにより、第一次検定の合格期限が無期限になったため、以前よりも施工管理技士の資格取得が簡単になりました。
\ 完全無料で内定までサポート /
※メールアドレスのみで登録できます
施工管理技士補を取得するメリット
施工管理技士補を取得するメリットは以下の通りです。
1級であれば「監理技術者補佐」として働くことができる
施工管理技士補を取得するメリットの1つ目は、1級施工管理技士補であれば「監理技術者補佐」として働くことができることです。
「「監理技術者補佐」という役割が新設」で解説した通り、1級施工管理技士補を取得することで、「監理技術者」に複数現場(2つまで)を兼任させるために必要な「監理技術者補佐」になることができます。
「監理技術者補佐」として働くことにより、通常5年ほど必要な実務経験が、1年間の実務経験で1級施工管理技士に挑戦できるというメリットもあります。
1級施工管理技士の最新の受検資格の詳細については、【2025年最新】1級建築施工管理技士の受検資格は?新旧条件と緩和措置を解説をご参照ください。
就職や転職で有利に働く
施工管理技士補を取得するメリットの2つ目は、就職や転職で有利に働くことです。
施工管理技士補は、「監理技術者補佐」などの施工管理技士の補佐を行うことができる資格です。
現在は建設業全体の人手不足により、施工管理技士の有資格者数も減少しているため、施工管理技士補の有資格者であっても「喉から手が出るほど欲しい!」という企業は多いでしょう。
また、実務・法的な役割に加えて、施工管理技士補を取得しているだけで「やる気がある」「基礎知識がある」と判断されるため、企業から評価されやすいというメリットもあります。
無資格者よりも仕事を任せてもらいやすい
施工管理技士補を取得するメリットの3つ目は、無資格者よりも仕事を任せてもらいやすいことです。
国家資格である「施工管理技士補」の資格を取得しているということは、無資格者よりも施工管理に関する知識や技術があると判断されるからです。
企業としてもなるべく早く施工管理技士を取得してほしいため、早いうちから様々な業務を経験させてくれるでしょう。
\ 完全無料で内定までサポート /
※メールアドレスのみで登録できます
施工管理技士補(施工管理技術検定第一次検定)の試験概要
1級・2級施工管理技士補になるには、施工管理技術検定の第一次検定に合格する必要があります。
ここでは、施工管理技術検定 一次試験の試験内容・受験資格・合格ラインについて解説します。
試験内容
1級・2級施工管理技術検定の第一次検定の試験内容は以下の通りです。
■1級・2級施工管理技術検定の第一次検定の試験内容
| 試験名 | 出題形式 | 出題内容 |
|---|---|---|
| 1級施工管理技術検定 第一次検定 | 4択・マークシート | 監理技術者補佐として、施工管理を適確に行うために必要な知識および応用能力に関する問題 |
| 2級施工管理技術検定 第一次検定 | 4択・マークシート | 施工管理を適確に行うために必要な基礎的な知識および能力に関する問題 |
細かい出題内容は、下表に記載の各指定試験機関HPでご確認ください。
■施工管理の種類別指定機関
| 検定種目 | 指定試験機関ホームページ |
|---|---|
| 建築施工管理(1級・2級) | (一財)建設業振興基金 |
| 電気工事施工管理(1級・2級) | (一財)建設業振興基金 |
| 土木施工管理(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
| 管工事施工管理(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
| 電気通信工事施工管理(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
| 造園施工管理(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
| 建設機械施工管理(1級・2級) | (一社)日本建設機械施工協会 |
受験資格
1級・2級施工管理技術検定の第一次検定の受験資格は以下の通りです。
■1級・2級施工管理技術検定の第一次検定の受験資格
| 試験名 | 受験資格 |
|---|---|
| 1級施工管理技術検定 第一次検定 | 満19歳以上(受験年度末時点) |
| 2級施工管理技術検定 第一次検定 | 満17歳以上(受験年度末時点) |
上記の通り、年齢さえクリアしており第一次検定を受験して合格すれば、1級・2級施工管理技士補になることができます。
合格基準
1級・2級施工管理技術検定の第一次検定の合格基準は以下の通りです。
1級については、施工管理法(応用能力)の得点基準が設けられている場合があるため、注意してください。
■1級・2級施工管理技術検定の第一次検定の合格基準
| 資格名 | 第一次検定の合格基準 | |
|---|---|---|
| 建築施工管理技士補 | 1級 | 全体の得点が60%以上 かつ 施工管理法(応用能力)の得点が60%以上 |
| 2級 | 全体の得点が60%以上 | |
| 電気工事施工管理技士補 | 1級 | 全体の得点が60%以上 かつ 施工管理法(応用能力)の得点が50%以上 |
| 2級 | 全体の得点が60%以上 | |
| 土木施工管理技士補 | 1級 | 全体の得点が60%以上 かつ 施工管理法(応用能力)の得点が60%以上 |
| 2級 | 全体の得点が60%以上 | |
| 管工事施工管理技士補 | 1級 | 全体の得点が60%以上 かつ 施工管理法(応用能力)の得点が50%以上 |
| 2級 | 全体の得点が60%以上 | |
| 電気通信工事施工管理技士補 | 1級 | 全体の得点が60%以上 かつ 施工管理法(応用能力)の得点が40%以上 |
| 2級 | 全体の得点が60%以上 | |
| 造園施工管理技士補 | 1級 | 全体の得点が60%以上 かつ 施工管理法(応用能力)の得点が30%以上 |
| 2級 | 全体の得点が60%以上 | |
| 建設機械施工管理技士補 | 1級 | 全体の得点が60%以上 |
| 2級 | 全体の得点が60%以上 | |
施工管理技士補の合格率は?
令和6年度直近の試験における各施工管理技士補の合格率は、以下の表の通りです。
種目によってばらつきはありますが、1級施工管理技士補が25%〜55%、2級施工管理技士補が40〜70%程度となっています。
■施工管理技士補の合格率
| 検定種目 | 1級 (合格者数/受験者数) |
2級 (合格者数/受験者数) |
|---|---|---|
| 建築施工管理技士補 | 36.2% (13,624人 / 37,651人) |
50.5% (11,550人 / 22,885人) |
| 電気工事施工管理技士補 | 36.7% (8,784人 / 23,927人) |
47.5% (2,730人 / 5,751人) |
| 土木施工管理技士補 | 44.4% (22,705人 / 51,193人) |
43.0% (5,840人 / 13,593人) |
| 管工事施工管理技士補 | 52.3% (12,147人 / 23,240人) |
65.1% (6,131人 / 9,413人) |
| 電気通信工事施工管理技士補 | 40.5% (3,240人 / 7,997人) |
68.6% (1,488人 / 2,169人) |
| 造園施工管理技士補 | 45.4% (1,566人 / 3,451人) |
51.1% (740人 / 1,447人) |
| 建設機械施工管理技士補 | 27.8% (773人 / 2,777人) |
41.2% (2,862人 / 6,950人) |
\ 完全無料で内定までサポート /
※メールアドレスのみで登録できます
施工管理技士補から施工管理技士になるためには
施工管理技士補から施工管理技士になるためには、1級・2級ともに第二次検定を受験して合格する必要があります。
第二次検定の受験には、各施工管理技術検定で定められている受験資格を満たす必要があります。
■関連記事
各施工管理技士 二次試験の受験資格は以下の記事で解説しています。
\ 完全無料で内定までサポート /
※メールアドレスのみで登録できます
まとめ
この記事では以下について解説しました。
■この記事のまとめ
施工管理技士補は、施工管理技士の補佐的な役割を担う国家資格です。
この資格を取得することで、建設現場での実務経験を早く積むことができ、将来的な施工管理技士資格の取得にも役立つでしょう。
また、1級施工管理技士補は、「監理技術者(1級施工管理技士)」に複数現場(2つまで)を兼任させるために必要な、「監理技術者補佐」を担当することができます。
さらに、施工管理技士補を取得することで就職や転職時のアピールポイントとなり、企業から評価される機会も増えるでしょう。
この資格が新設された背景には、建設業界全体の人手不足や、法律で定められた「監理技術者」の不足を解消する狙いがあります。
若手技術者が挑戦しやすい環境を作ることで、建設業界の未来を支える人材を育てる仕組みの一環として、この制度が導入されました。
これから施工管理の仕事をしていきたい方は、まず「施工管理技士補」を目指してみてください。
\ 完全無料で内定までサポート /
※メールアドレスのみで登録できます
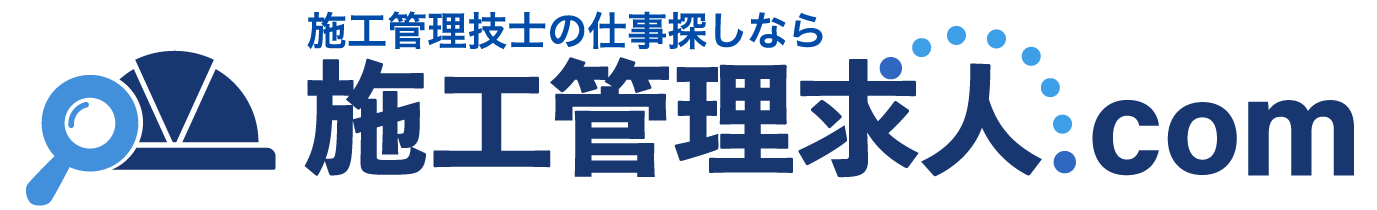
 閲覧履歴
閲覧履歴 気になる
気になる ログイン
ログイン