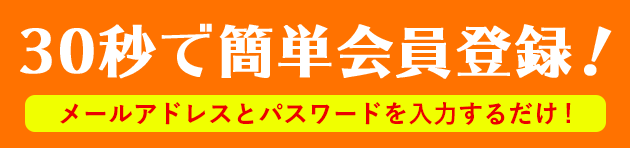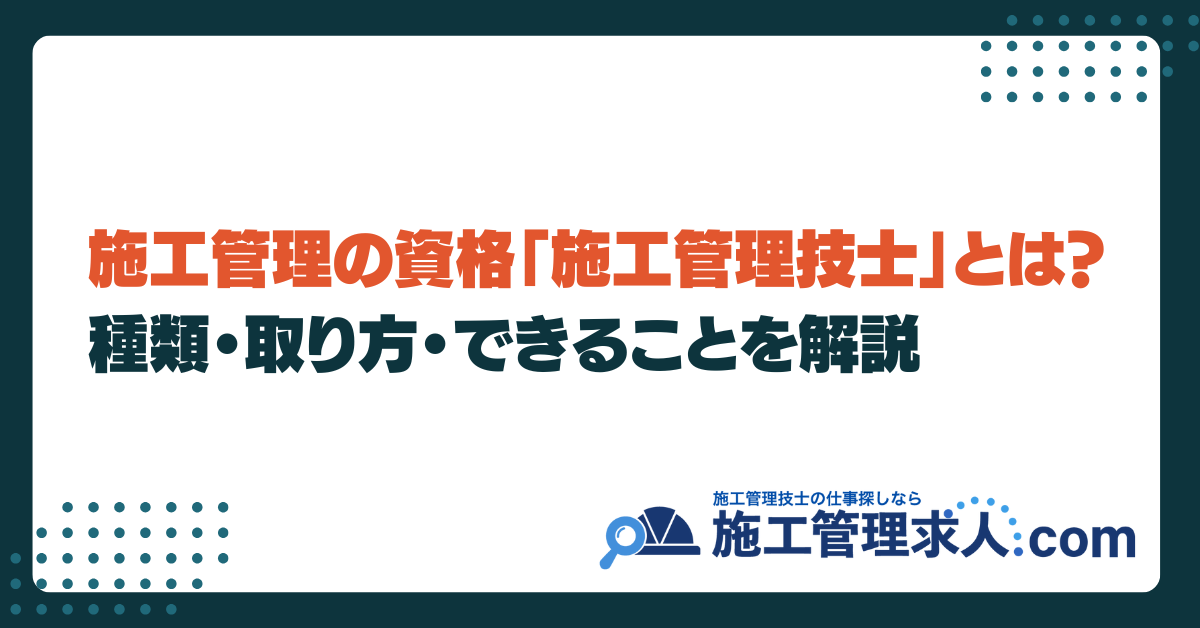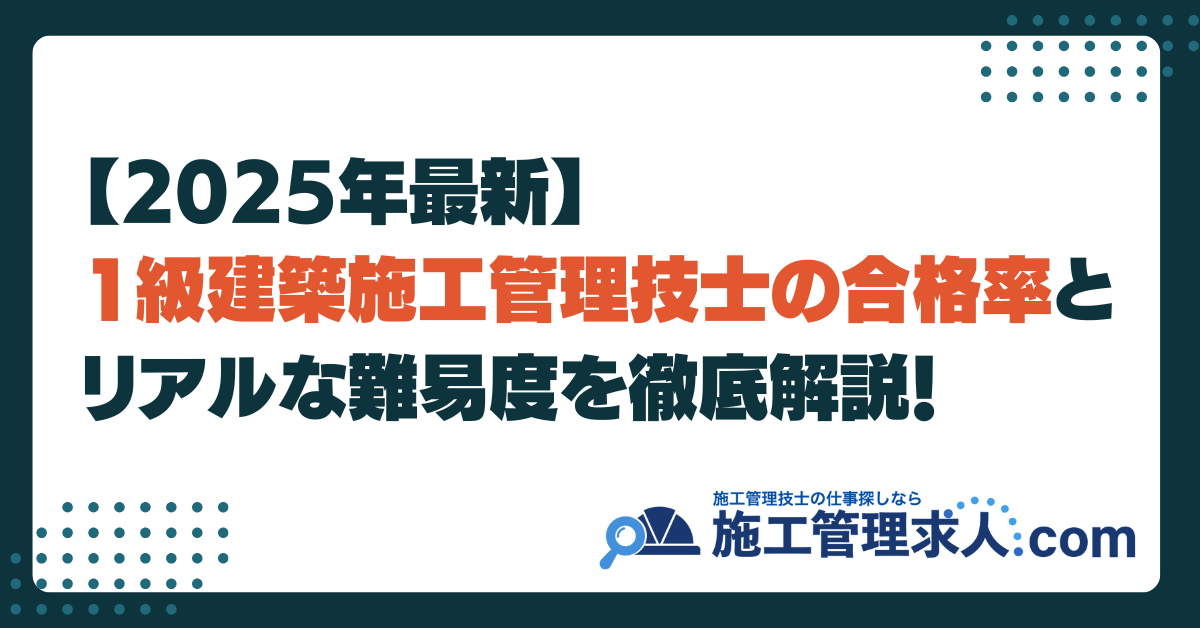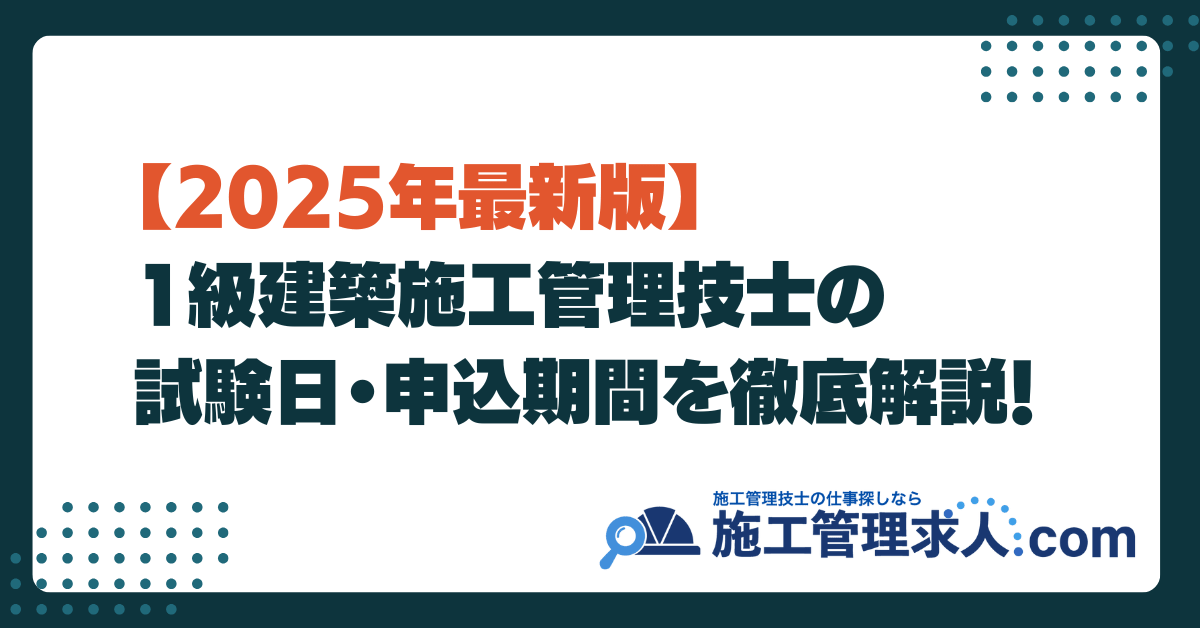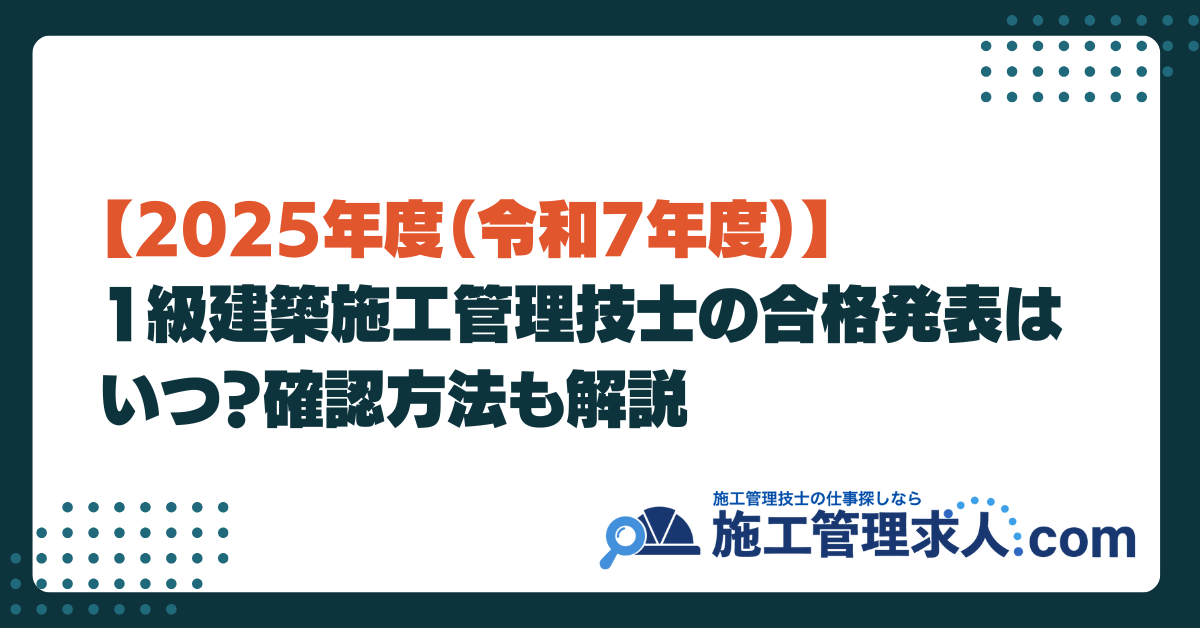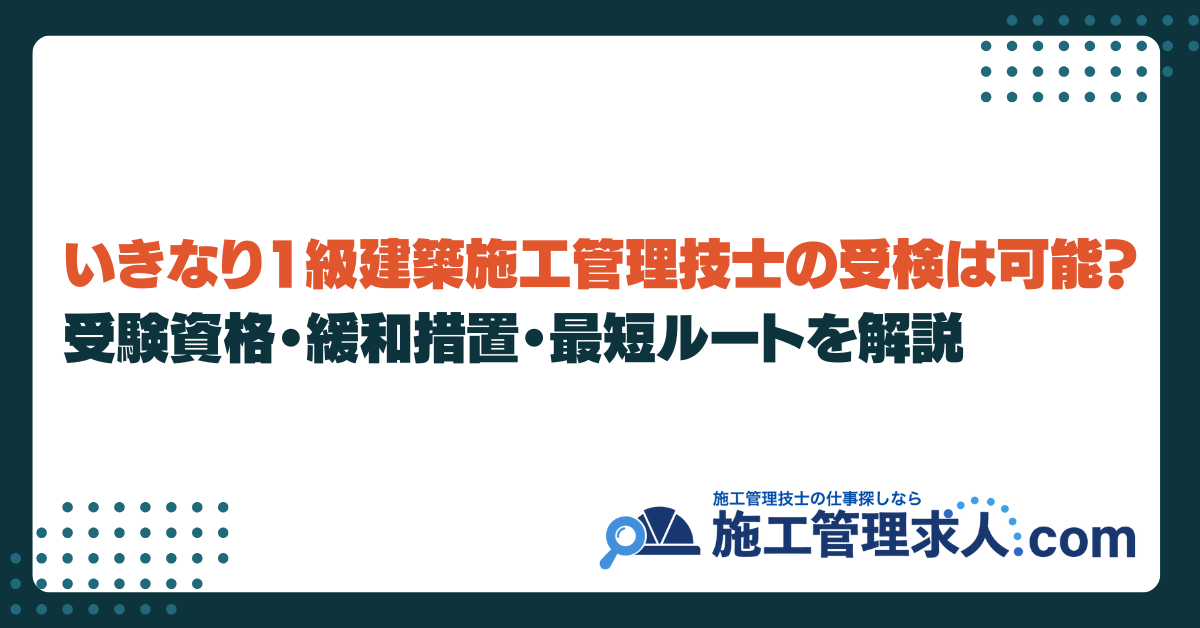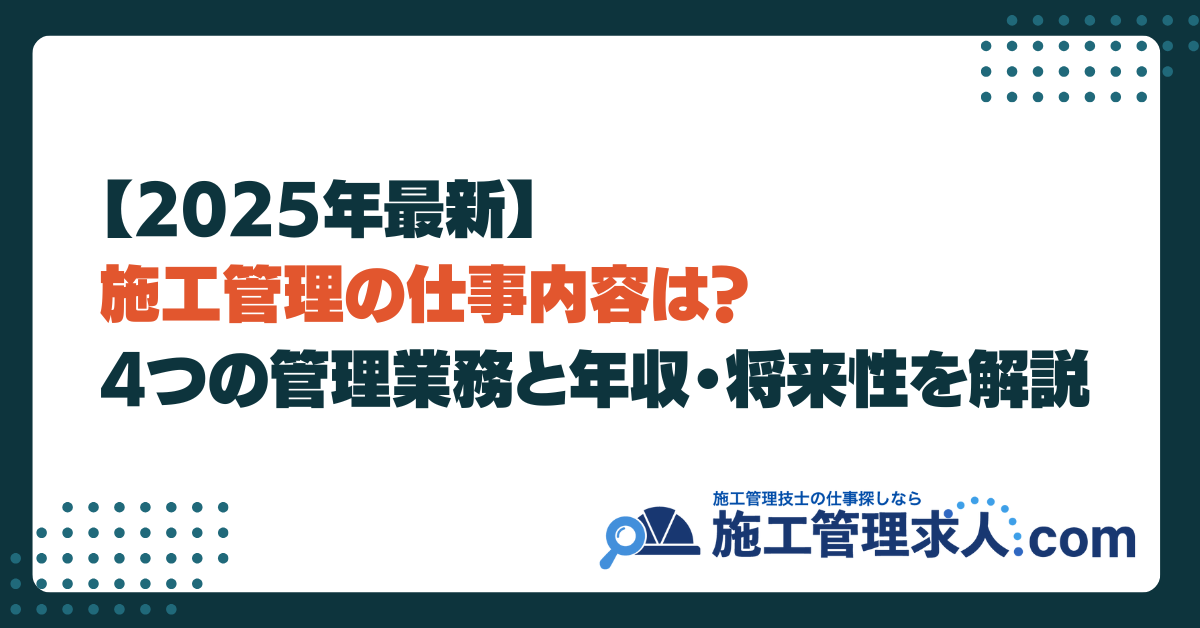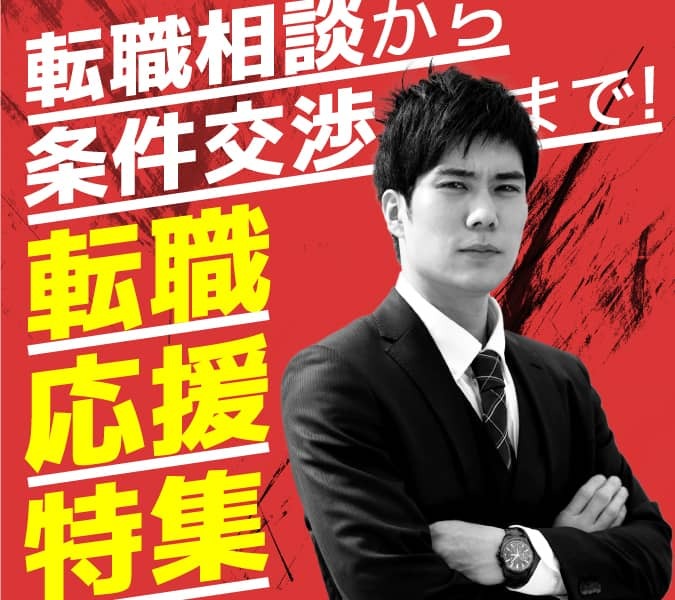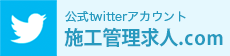- 1級建築施工管理技士 第一次検定の最新受検資格
- 1級建築施工管理技士 第二次検定の最新受検資格(新旧制度・経過措置)
- 学歴や実務経験に応じた具体的な受検資格パターン
- 実務経験として認められる工事・業務の具体例と注意点
- 受検資格に関するよくある質問への回答
【2025年最新】1級建築施工管理技士の受検資格は?新旧条件と緩和措置を解説
最終更新日:
1級建築施工管理技士の受検資格は、第一次検定が19歳以上であれば学歴・実務経験不問、第二次検定は第一次検定合格後の実務経験が必要となります。(令和6年度改正)
これに加えて令和10年度までは、旧受検資格の条件に当てはまってさえいれば、第二次検定の受検が可能となる経過措置も適用されています。
現状適用されている受検資格は以下の表でご確認ください。
| 検定区分 | 制度 | 前提資格 | 学歴・学科(旧制度) | 必要な実務経験 | 備考・注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一次検定 | 新制度 (R6年度~) | なし | 不問 | なし | 満19歳以上(受検年度末時点)であれば誰でも受検可能 |
| 第二次検定 | 新制度 (R6年度~) | 1級第一次検定 合格 | 不問 | ①実務経験 5年以上 ②特定実務経験1年以上含む実務経験 3年以上 ③監理技術者補佐 実務経験 1年以上 |
①~③のいずれか 特定実務経験・監理技術者補佐の定義は本文参照 |
| 2級第二次検定 合格 + 1級第一次検定 合格 | 不問 | ①実務経験 5年以上 ②特定実務経験1年以上含む実務経験 3年以上 |
①または② 2級合格後の経験年数 |
||
| 一級建築士 合格 | 不問 | ①実務経験 5年以上 ②特定実務経験1年以上含む実務経験 3年以上 |
①または② 一級建築士合格後の経験年数 |
||
| 旧制度 (経過措置) | 1級第一次検定 合格 or 一級建築士 合格 | 大学・高度専門士(指定学科) | 卒業後 3年以上(指導監督1年以上含む) |
令和10年度まで利用可能 指導監督的実務経験1年以上必須 短縮措置あり(本文参照) |
|
| 大学・高度専門士(指定学科以外) | 卒業後 4年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) | 同上 | |||
| 短大・高専・専門士(指定学科) | 卒業後 5年以上(指導監督1年以上含む) | 同上 | |||
| 短大・高専・専門士(指定学科以外) | 卒業後 7年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) | 同上 | |||
| 高校・専門課程(指定学科) | 卒業後 10年以上(指導監督1年以上含む) (※注2)(※注3) |
同上 | |||
| 高校・専門課程(指定学科以外) | 卒業後 11年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| その他(学歴不問) | 15年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 2級第二次検定 合格 | 短大・高専・専門士(指定学科以外) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注2)(※注3) |
同上 | ||
| 高校・専門課程(指定学科) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 高校・専門課程(指定学科以外) | 卒業後 10年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| その他(学歴不問) | 通算 14年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 短大・高専・専門士(指定学科以外) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 高校・専門課程(指定学科) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 二級建築士 合格 | - | 合格後 5年以上(指導監督1年以上含む) | 同上 |
- (※注2) 主任技術者の要件を満たした後に、専任の監理技術者の指導の下で2年以上の実務経験がある場合、必要な実務経験年数が2年短縮されます
- (※注3) 専任の主任技術者としての経験が1年以上ある場合、必要な実務経験年数が2年短縮されます(詳細な要件あり)
「自分の学歴や実務経験で本当に受検できるのだろうか?」そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?
1級建築施工管理技士の受検資格は令和6年度から改定され、新受検資格と旧受検資格が混在しているため、とても複雑になっています。
この記事では、令和7年度(2025年度)試験に対応した1級建築施工管理技士の最新受検資格を、試験実施機関である一般財団法人 建設業振興基金 が発表する最新の「受検の手引」に基づき徹底解説します。
新旧制度の違いや令和10年度までの経過措置、学歴・実務経験別の必要年数、認められる工事内容まで、あなたが受検資格を満たしているか明確に判断できるよう、分かりやすく説明します。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりも良い職場で働く
【2025年度最新】1級建築施工管理技士の受検資格とは?令和6年度からの変更点を解説
まずは1級建築施工管理技士の受検資格の全体像と、令和6年度からの大きな変更点について解説します。新旧制度の違いを把握することが、ご自身の受検資格を正しく理解する第一歩です。
1級建築施工管理技士の受検資格
1級建築施工管理技士の受検資格は、第一次検定が19歳以上であれば学歴・実務経験不問、第二次検定は第一次検定合格後の実務経験が必要となります。(令和6年度改正)
これに加えて令和10年度までは、旧受検資格の条件に当てはまってさえいれば、第二次検定の受検が可能となる経過措置も適用されています。
現状適用されている受検資格は以下の表でご確認ください。
| 検定区分 | 制度 | 前提資格 | 学歴・学科(旧制度) | 必要な実務経験 | 備考・注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一次検定 | 新制度 (R6年度~) | なし | 不問 | なし | 満19歳以上(受検年度末時点)であれば誰でも受検可能 |
| 第二次検定 | 新制度 (R6年度~) | 1級第一次検定 合格 | 不問 | ①実務経験 5年以上 ②特定実務経験1年以上含む実務経験 3年以上 ③監理技術者補佐 実務経験 1年以上 |
①~③のいずれか 特定実務経験・監理技術者補佐の定義は本文参照 |
| 2級第二次検定 合格 + 1級第一次検定 合格 | 不問 | ①実務経験 5年以上 ②特定実務経験1年以上含む実務経験 3年以上 |
①または② 2級合格後の経験年数 |
||
| 一級建築士 合格 | 不問 | ①実務経験 5年以上 ②特定実務経験1年以上含む実務経験 3年以上 |
①または② 一級建築士合格後の経験年数 |
||
| 旧制度 (経過措置) | 1級第一次検定 合格 or 一級建築士 合格 | 大学・高度専門士(指定学科) | 卒業後 3年以上(指導監督1年以上含む) |
令和10年度まで利用可能 指導監督的実務経験1年以上必須 短縮措置あり(本文参照) |
|
| 大学・高度専門士(指定学科以外) | 卒業後 4年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) | 同上 | |||
| 短大・高専・専門士(指定学科) | 卒業後 5年以上(指導監督1年以上含む) | 同上 | |||
| 短大・高専・専門士(指定学科以外) | 卒業後 7年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) | 同上 | |||
| 高校・専門課程(指定学科) | 卒業後 10年以上(指導監督1年以上含む) (※注2)(※注3) |
同上 | |||
| 高校・専門課程(指定学科以外) | 卒業後 11年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| その他(学歴不問) | 15年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 2級第二次検定 合格 | 短大・高専・専門士(指定学科以外) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注2)(※注3) |
同上 | ||
| 高校・専門課程(指定学科) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 高校・専門課程(指定学科以外) | 卒業後 10年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| その他(学歴不問) | 通算 14年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 短大・高専・専門士(指定学科以外) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 高校・専門課程(指定学科) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
同上 | |||
| 二級建築士 合格 | - | 合格後 5年以上(指導監督1年以上含む) | 同上 |
- (※注2) 主任技術者の要件を満たした後に、専任の監理技術者の指導の下で2年以上の実務経験がある場合、必要な実務経験年数が2年短縮されます
- (※注3) 専任の主任技術者としての経験が1年以上ある場合、必要な実務経験年数が2年短縮されます(詳細な要件あり)
令和6年度からの主な変更点まとめ(新旧比較表)
令和6年度の技術検定制度改正により、1級建築施工管理技士の受検資格は大きく見直されました。主な変更点は以下の通りです。
| 検定区分 | 変更点 | 旧制度(令和5年度まで) |
|---|---|---|
| 第一次検定 | 受検資格の緩和 | 学歴に応じた実務経験が必要 |
| 第二次検定 | 第一次検定合格後の実務経験が必要に | 第一次検定合格+学歴に応じた実務経験 |
| 旧制度の経過措置 | - | |
| 技士補資格 | 第二次検定受検資格との関連強化 | 第一次検定合格で技士補に。第二次受検資格とは直接関連せず |
この改正により、第一次検定への挑戦のハードルは下がりました。
ただ、第二次検定を受検するためには、依然として第一次検定に合格した後の実務経験が必要になります。

令和10年度までは旧制度の受検資格も利用できる経過措置が設けられています。
効率良く資格を取得するためには、自分がどの受検資格を利用すれば早く受検できるのかを考え、計画を立てることが重要です。
なぜ受検資格が変わった?改正の背景
今回の受検資格見直しの背景には、建設業界が抱えるいくつかの課題があります。
国土交通省の発表などによると、建設業界では技術者の高齢化が進み、将来の担い手確保が喫緊の課題となっています。特に、大規模工事に必要な監理技術者の不足が懸念されています。
また、若年層の入職者を増やし、早期にキャリアアップできる道筋を示すことも重要です。
このような状況を踏まえ、令和3年度に施工管理技士補の資格が創設され、監理技術者の配置義務が緩和されました。今回の受検資格改正は、この技士補制度との連携を強化し、若手技術者がより早い段階で第一次検定に挑戦し、技士補として経験を積みながら第二次検定を目指せるように、段階的なステップアップを促すことを目的としています。
第一次検定の門戸を広げることで、建設業界への関心を高め、将来の優秀な技術者を育成しようという狙いがあるのです。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりも良い職場で働く
【この見出しのまとめ】
- 令和6年度から受検資格が改正され、第一次検定は19歳以上なら誰でも受検可能に。
- 第二次検定は第一次合格後の実務経験が必要だが、令和10年度までは旧制度も利用可能。
- 改正の背景には、技術者不足解消と若手育成、技士補制度との連携がある。
【第一次検定】受検資格は「19歳以上」のみ!学歴・実務経験不問に
令和6年度から最も大きく変わったのが第一次検定の受検資格です。
これまで必要だった学歴や実務経験の要件が撤廃され、非常にシンプルになりました。
令和6年度以降の1級建築施工管理技士 第一次検定の受検資格は、「受検する年度の末日時点で満19歳以上であること」という年齢要件のみです。
具体的には、令和7年度(2025年度)の試験を受検する場合、平成18年(2006年)3月31日までに生まれた方であれば、誰でも受検資格があります。
学歴(大学、短大、高専、高校、専門学校など)や卒業した学科(指定学科か否か)、これまでの実務経験年数は一切問われません。
外国籍の方でも、この年齢要件を満たせば受検可能です。
これにより、例えば実務経験がまだない建築系の学生や、これまで学歴要件で受検できなかった方も、1級建築施工管理技士補を目指して第一次検定に挑戦できるようになりました。
「いきなり1級」の第一次検定に挑戦できるようになった点は、大きな変更点と言えるでしょう。2級建築施工管理技士の試験を受検せずにいきなり1級建築施工管理技士の試験を受検できるかどうかについては、「いきなり1級建築施工管理技士は可能?受検資格・緩和措置・最短ルートを解説」も参考にしてください。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりも良い職場で働く
【この見出しのまとめ】
- 1級建築施工管理技士 第一次検定の受検資格は、受検年度末時点で満19歳以上であることのみ。
- 学歴や実務経験は一切問われないため、多くの方が挑戦しやすくなった。
【第二次検定】受検資格をパターン別に徹底解説!新旧制度と経過措置も確認
第一次検定に合格し、1級建築施工管理技士の資格を取得するには、第二次検定に合格する必要があります。
第二次検定の受検資格は、第一次検定とは異なり、実務経験が求められます。
令和6年度の制度改正により、第二次検定の受検資格も変更されました。ただし、令和10年度までは経過措置として、改正前の旧制度の受検資格でも受検が可能です。
ここでは、新制度と旧制度(経過措置)それぞれの受検資格パターンを詳しく解説します。

ご自身の状況に合わせて、どちらの制度を利用できるか、どちらが有利かを確認しましょう。
【新制度】第二次検定の受検資格パターン(第一次合格後)
令和6年度以降の新制度では、1級建築施工管理技術検定の第一次検定に合格した後、以下のいずれかの実務経験要件を満たすことで第二次検定を受検できます。
■新制度における第二次検定 受検資格
| 前提条件 | 学歴・学科(旧制度) | 必要な実務経験 |
|---|---|---|
| 1級第一次検定 合格 | 不問 | ①実務経験 5年以上 ②特定実務経験1年以上含む実務経験 3年以上 ③監理技術者補佐 実務経験 1年以上 |
| 2級第二次検定 合格 + 1級第一次検定 合格 | 不問 | ①実務経験 5年以上 ②特定実務経験1年以上含む実務経験 3年以上 |
| 一級建築士 合格 | 不問 | ①実務経験 5年以上 ②特定実務経験1年以上含む実務経験 3年以上 |
※出典 一般財団法人 建設業振興基金「受検の手引【分冊(新受検資格用)】」
【用語解説】
- 特定実務経験とは
- 請負金額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者または主任技術者(いずれも監理技術者資格者証を持つ者)の指導の下で行った施工管理経験、または自らが監理技術者・主任技術者として行った施工管理経験を指します。
- 発注者側での経験や、建設業法の技術者配置義務がない小規模工事などは含まれません。
- 監理技術者補佐とは
- 1級建築施工管理技士補の資格を持ち、かつ主任技術者の資格要件を満たす者が、監理技術者の専任が必要な工事において、監理技術者の職務を専任で補佐した経験を指します。単なる補助業務は含まれません。
新制度では、学歴に関わらず、第一次検定合格後の実務経験年数で判断されるのが特徴です。
特に、1級技士補として監理技術者補佐の経験を1年積めば、最短で第二次検定に挑戦できるルートが設けられました。
監理技術者補佐としての実務経験には、まず1級建築施工管理技士補の資格が必要です。技士補については「施工管理技士補とは?取得のメリットや試験概要・合格率・取得方法を徹底解説!」で詳しく解説しています。
【旧制度・経過措置】第二次検定の受検資格パターン(令和10年度まで)
令和6年度から新制度が導入されましたが、令和10年度(2028年度)の試験までは、経過措置として従来の旧制度の受検資格でも第二次検定を受検することが可能です。
旧制度では、1級建築施工管理技術検定の第一次検定合格(または一級建築士試験合格)に加え、最終学歴と指定学科の卒業有無によって必要な実務経験年数が定められています。
■旧制度における第二次検定 受検資格パターン(学歴別)
| 最終学歴 | 指定学科 卒業 | |
|---|---|---|
| 1級第一次検定 合格 or 一級建築士 合格 | 大学・高度専門士(指定学科) | 卒業後 3年以上(指導監督1年以上含む) |
| 大学・高度専門士(指定学科以外) | 卒業後 4年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) | |
| 短大・高専・専門士(指定学科) | 卒業後 5年以上(指導監督1年以上含む) | |
| 短大・高専・専門士(指定学科以外) | 卒業後 7年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) | |
| 高校・専門課程(指定学科) |
卒業後 10年以上(指導監督1年以上含む) (※注2)(※注3) |
|
| 高校・専門課程(指定学科以外) | 卒業後 11年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
|
| その他(学歴不問) | 15年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
|
| 2級第二次検定 合格 | - | 合格後 5年以上(指導監督1年以上含む) (※注2)(※注3) |
| 短大・高専・専門士(指定学科以外) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
|
| 高校・専門課程(指定学科) | 卒業後 9年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
|
| 高校・専門課程(指定学科以外) | 卒業後 10年6ヶ月以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
|
| その他(学歴不問) | 通算 14年以上(指導監督1年以上含む) (※注3) |
|
| 二級建築士 合格 | - | 合格後 5年以上(指導監督1年以上含む) |
※出典 一般財団法人 建設業振興基金「受検の手引【総合版(旧受検資格用)】」
【旧制度の重要ポイント】
- 上記の実務経験年数には、1年以上の指導監督的実務経験を含む必要があります
- 指導監督的実務経験とは、現場代理人、主任技術者、工事主任、設計監理者、施工監督などの立場で、部下や下請け業者に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験を指します
- 実務経験年数の短縮措置があります
- (※注2) 主任技術者の要件を満たした後に、専任の監理技術者の指導の下で2年以上の実務経験がある場合、必要な実務経験年数が2年短縮されます
- (※注3) 専任の主任技術者としての経験が1年以上ある場合、必要な実務経験年数が2年短縮されます(詳細な要件あり)
- 指定学科とは、建築学、土木工学など、国土交通省令で定められた学科を指します。詳細は試験実施機関のWebサイトで確認できます
【旧制度における資格保有者の優遇措置】
- 二級建築士試験合格者
合格後 5年以上 の実務経験(指導監督的実務経験1年以上含む)で受検可能 - 2級建築施工管理技士 第二次検定合格者
- 合格後 5年以上 の実務経験(指導監督的実務経験1年以上含む)で受検可能 (※注2, 注3の短縮措置対象)
- 合格後5年未満でも、学歴に応じた実務経験年数(例 高卒指定学科なら9年以上)を満たせば受検可能
旧制度の受検資格については、「建築施工管理技士の受検資格とは?|1級・2級の技術検定について解説!」の記事でも詳しく解説しています。
あなたはどっち?新旧どちらの制度で受検すべきか
令和10年度までは新旧どちらの制度でも受検申請が可能ですが、どちらを選ぶべきか迷う方もいるでしょう。判断のポイントは以下の通りです。
- 第一次検定にいつ合格したか(または合格見込みか)
- 令和6年度以降に第一次検定に合格した場合、基本的には新制度の要件(第一次合格後の実務経験)で第二次検定を目指すことになります。
- 令和5年度以前に第一次検定に合格している場合、旧制度の学歴+実務経験要件を満たしていれば、すぐに第二次検定を受検できます。
- 最終学歴と指定学科の有無
- 大学や専門学校で指定学科を卒業している方は、旧制度の方が短い実務経験年数で受検できる可能性があります。
- 高卒の方や指定学科以外の方は、新制度の方が有利になる場合があります(ただし第一次合格後の経験が必要)。
- 実務経験の内容と年数
- 特定実務経験や監理技術者補佐の経験がある方は、新制度で最短ルート(3年または1年)を目指せます。
- 指導監督的実務経験が1年以上ある方は、旧制度の要件を満たしやすい可能性があります。
経過措置期間(令和10年度まで)は、ご自身の状況をよく確認し、有利な方の制度を選択して申請することが重要です。
不明な点は、必ず試験実施機関に確認しましょう。
1級建築施工管理技士補からの受検ルート
令和3年度に新設された「1級建築施工管理技士補」は、1級建築施工管理技術検定の第一次検定に合格することで取得できる資格です。
1級建築施工管理技士補の資格を持っている方は、新制度において第二次検定の受検資格を得る上で有利になります。
- 技士補として実務経験を積む
第一次検定合格後、技士補として実務経験を積みます。 - 第二次検定の受検資格
- 実務経験5年以上
- 特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
- 監理技術者補佐としての実務経験1年以上
特に、監理技術者補佐として1年以上の実務経験を積めば、最短で第二次検定の受検資格を得られる点が大きなメリットです。
1級建築施工管理技士補のメリットや役割について、詳しくはこちらをご覧ください。 「施工管理技士補とは?取得のメリットや試験概要・合格率・取得方法を徹底解説!」
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりも良い職場で働く
【この見出しのまとめ】
- 第二次検定は第一次合格後の実務経験が必要(新制度)
- 令和10年度までは旧制度(学歴+実務経験)でも受検可能(経過措置)
- 新制度では特定実務経験や監理技術者補佐経験で必要年数が短縮される
- 自身の状況に合わせて有利な制度を選択することが重要
- 1級建築施工管理技士補からの最短ルートは監理技術者補佐1年
実務経験として認められる工事・業務とは?具体例と注意点
受検資格で最も重要かつ判断が難しいのが「実務経験」です。どのような工事や業務が実務経験として認められるのか、具体例と注意点を解説します。
ここで間違うと受検資格を満たせない可能性があるため、しっかり確認しましょう。
実務経験として認められる建築工事の具体例
1級建築施工管理技士の受検資格として認められる実務経験は、建築工事の施工に直接関わる技術上の職務経験です。
具体的には、以下の工事における施工管理、施工監督、設計監理の経験が該当します。
【認められる工事種別の例】
| 工事種類 | 内容 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 事務所ビル、マンション、学校、病院、店舗、工場、戸建住宅などの新築、増築、改築工事全般 |
| 大工工事 | 型枠工事、造作工事など |
| とび・土工・コンクリート工事 | 足場仮設、鉄骨建方、PC設置、コンクリート打設、掘削、地盤改良など |
| 鋼構造物工事 | 鉄骨工事(建築物)、屋外広告物設置など |
| 鉄筋工事 | 鉄筋加工組立、ガス圧接など |
| タイル・れんが・ブロック工事 | タイル張り、レンガ積み、ALCパネル設置、サイディング工事など |
| 左官工事 | モルタル塗り、吹付け、洗い出しなど |
| 石工事 | 石積み、石張り、エクステリア工事など |
| 屋根工事 | 各種屋根ふき工事 |
| 板金工事 | 建築板金工事 |
| ガラス工事 | ガラス取付、ガラスフィルム工事など |
| 塗装工事 | 建築物の内外塗装工事 |
| 防水工事 | アスファルト防水、シート防水、シーリング工事など |
| 内装仕上工事 | インテリア、天井・壁・床仕上げ、間仕切り、家具、防音工事など |
| 建具工事 | 金属製・木製建具取付、サッシ、シャッター、自動ドア取付など |
| 熱絶縁工事 | 建築物の断熱工事など |
| 解体工事 | 建築物の解体工事 |
【認められる業務内容の例】
- 施工計画の作成
- 工程管理(スケジュール調整、進捗管理)
- 品質管理(材料検査、施工状況確認、出来形管理)
- 安全管理(現場巡視、安全教育、危険予知活動)
- 原価管理(実行予算作成、コスト管理)※施工管理業務の一環として行う場合
- 施工図の作成・チェック
- 下請業者との調整・指導監督
- 発注者や設計監理者との打ち合わせ
【判断に迷うケース】
| 工事・経験の種類 | 実務経験としての取り扱い |
|---|---|
| リフォーム・リノベーション工事 | 建築工事に該当する内容であれば実務経験として認められます |
| 解体工事 | 建築物解体工事は令和元年から建設業許可の業種に追加され、実務経験として認められます |
| 仮設工事 | 足場仮設など、建築工事本体に付随する仮設工事の施工管理経験は認められます |
| 発注者側・設計事務所側の経験 |
原則として対象外ですが、施工監督や設計監理の立場で現場の技術的な管理・指導に直接関与していた場合は認められる可能性があります 詳細は一般財団法人 建設業振興基金 への確認が必要です |
実務経験として認められない工事・業務
以下の工事や業務は、原則として1級建築施工管理技士の実務経験としては認められません。
【認められない工事の例】
| 工事種類 | 主な工事内容 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 道路、橋梁、トンネル、ダム、河川、港湾、下水道本管など |
| 電気工事 | 発電設備、送配電線、構内電気設備、信号設備など |
| 管工事 | 冷暖房設備、給排水衛生設備、ガス管配管、ダクト工事など(建築物に付帯する設備工事であっても、管工事として別途発注・施工管理されている場合) |
| 電気通信工事 | 通信線路、放送設備、データ通信設備など |
| 造園工事 | 植栽、公園設備、屋上緑化など(建築工事と一体でない場合) |
| 消防施設工事 | 消火栓、スプリンクラー、火災報知器など |
| その他 | 舗装工事、しゅんせつ工事、機械器具設置工事、さく井工事、水道施設工事、清掃施設工事など |
【認められない業務・立場の例】
- 設計業務のみ
基本設計、実施設計など、施工に直接関与しない業務 - 積算業務のみ
工事費の見積もり作成業務 - 保守・点検・維持管理業務
竣工後のメンテナンス業務 - 営業・事務・庶務
受注活動や一般的な事務作業 - 単なる作業員
施工管理の立場ではなく、指示を受けて作業を行う立場 - 測量・地盤調査業務のみ
- 資材管理・購買業務のみ
- CADオペレーター業務のみ
- 入社後の研修期間
- 人材派遣による建設作業(施工管理業務を除く)
建築工事の現場にいたとしても、施工管理(計画・工程・品質・安全など)に直接関与していない業務は実務経験として認められません。
ご自身の経験が該当するか不安な場合は、一般財団法人 建設業振興基金
試験研修本部に問い合わせることをおすすめします。
実務経験証明書の書き方と注意点
実務経験は、受検申込時に提出する「実務経験証明書」によって証明する必要があります。
この書類は非常に重要であり、不備があると受検資格が認められない場合があります。
【主な記載項目】
- 勤務先情報(会社名、所在地、建設業許可番号など)
- 工事情報(工事名、工事場所、工期、請負金額、発注者名など)
- 従事した立場(役職名)
- 担当した具体的な業務内容(施工計画、工程管理、品質管理、安全管理など)
- 従事期間
- 証明者の情報(氏名、役職など)
【証明者について】
- 原則として、工事ごとに、その工事期間中に在籍していた勤務先の代表者または工事の監理技術者・主任技術者による証明が必要です。
- 令和6年3月31日を含む工事経験までは、経過措置として、申請時に所属している会社の代表者等による証明も可能です。
- 転職した場合などは、それぞれの勤務先から証明をもらう必要があります。
- 自身が代表者の場合は自己証明となりますが、建設業許可通知書などの確認書類が必要です。
【期間計算の注意点】
- 実務経験年数は、原則として試験実施年度の前年度末(例 令和7年度試験なら令和7年3月31日)時点で計算します
- 年数が不足する場合、第二次検定試験日の前日までの予定実務経験を算入できますが、申請時点で契約済みの工事に限ります
- 複数の工事を同時期に担当した場合でも、期間の重複算入はできません。実際の従事割合に応じて按分する必要があります(異なる検定種目の場合)
【書き方のポイントと注意点】
- 具体的に記述する
工事内容や担当業務は、「〇〇工事における工程管理、安全管理」のように具体的に記載します。抽象的な表現は避けてください。 - 虚偽記載は厳禁
事実と異なる内容を記載した場合、合格取消や受検禁止措置の対象となります。 - 証明者要件を確認
正しい証明者(代表者、監理技術者など)に依頼してください。 - 新旧様式に注意
新受検資格で申請する場合は、必ず新受検資格用の実務経験証明書様式を使用してください(旧様式(C票)は使用できません)
様式は一般財団法人 建設業振興基金のWebサイトからダウンロードできます。 - 不明点は確認
書き方や実務経験の判断に迷う場合は、必ず事前に試験実施機関に問い合わせましょう。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりも良い職場で働く
【この見出しのまとめ】
- 実務経験は建築工事の施工管理・監督・設計監理経験が対象
- 土木工事や設備工事、事務作業などは原則対象外
- 実務経験証明書は工事ごとに証明が必要(原則)
- 虚偽記載は厳禁。不明点は必ず試験実施機関に確認する
受検資格に関するQ&A|よくある質問に答えます
ここでは、1級建築施工管理技士の受検資格に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でお答えします。
Q. いきなり1級を受検できますか?
令和6年度から1級の第一次検定は19歳以上なら誰でも受検可能ですが、資格取得には第一次検定合格後の実務経験が必要です。
第一次検定は学歴・実務経験不問となりましたが、第二次検定受検には第一次検定合格後の所定実務経験が必要です。一度に両方の検定に合格して資格取得することはできません。まずは第一次検定に合格し、1級建築施工管理技士補として実務経験を積むのが一般的です。
Q. 指定学科卒業でないと不利ですか?
新制度では指定学科卒業の有無は関係ありませんが、旧制度を利用する場合は指定学科卒業者が有利です。
令和6年度からの新制度では第一次検定は学歴不問、第二次検定も学歴に関わらず実務経験年数(5年/特定実務含む3年/補佐1年)で判断されます。ただし、令和10年度までの経過措置期間中に旧制度で受検する場合は、指定学科卒業者の方が短い実務経験で受検できます。
Q. 実務経験の証明が難しい場合はどうすればいいですか?
実務経験証明が難しい場合は、まず一般財団法人建設業振興基金試験研修本部に早めに相談してください。
過去の勤務先が倒産している、上司と連絡が取れないなどの場合、状況によっては代替書類(雇用契約書、出張命令書、経費精算書など)での証明が認められる可能性があります。
Q. 受検資格が緩和されたのはいつからですか?
1級建築施工管理技士の受検資格緩和を含む制度改正は令和6年度(2024年度)の試験から適用されています。
令和7年度(2025年度)の試験も、この改正後の受検資格に基づいて実施されます。
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりも良い職場で働く
まとめ|受検資格を確認して1級建築施工管理技士を目指そう
この記事では、令和7年度(2025年度)試験に対応した1級建築施工管理技士の最新の受検資格について、令和6年度からの変更点を中心に詳しく解説しました。
- 第一次検定は、受検年度末時点で満19歳以上であれば、学歴・実務経験不問で誰でも受検可能。
- 第二次検定は、第一次検定合格後に実務経験5年または特定実務経験1年以上を含む実務経験3年、または監理技術者補佐としての実務経験1年が必要(新制度)
- 令和10年度までは、従来の旧制度(学歴+実務経験)でも第二次検定の受検が可能
- 建築工事の施工管理経験が対象であるため、認められる工事・業務、証明方法を正確に理解することが重要
- 必ず一般財団法人 建設業振興基金 試験研修本部が発表する最新の「受検の手引」で最終確認を
ご自身の学歴や実務経験を照らし合わせ、受検資格を満たしているか確認できたでしょうか。受検資格を知ることは資格取得への第一歩です。
受検資格をクリアしたら、次は試験合格に向けた学習計画や、資格取得後のキャリアプランを具体的に考えていく段階です。
1級建築施工管理技士の資格は、昇進や転職において大きな武器となり、あなたの市場価値を高めてくれます。 関連情報として、「【2025年最新】1級建築施工管理技士の合格率とリアルな難易度を徹底解説!」や「【2025年最新版】1級建築施工管理技士の試験日・申込期間を徹底解説!」も参考にしてください。
「資格を活かしてどんなキャリアが描けるだろう?」「自分に合った企業を見つけたい」
もし、そんな風にお考えなら、建設・施工管理業界に特化した転職エージェント「施工管理求人.com」にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーが、あなたの経験や希望に合った求人紹介はもちろん、キャリアプランに関する無料相談も行っています。非公開求人も多数保有しており、あなたの可能性を広げるお手伝いができます。
まずは無料登録から、あなたのキャリアの可能性を探ってみませんか?
\ 資格を活かして転職を成功させる /
※たった1分の登録で今よりも良い職場で働く
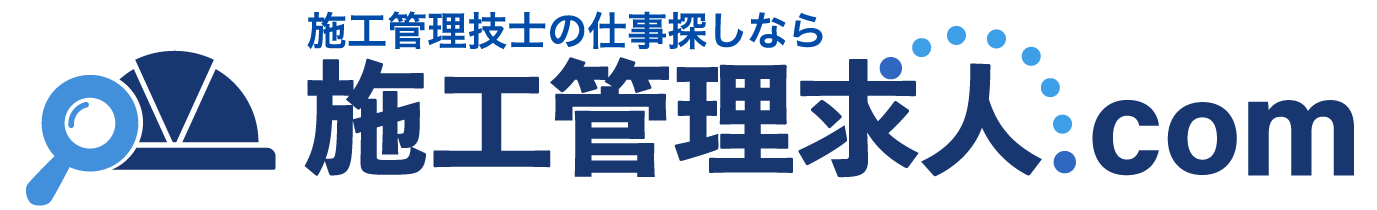
 閲覧履歴
閲覧履歴 気になる
気になる ログイン
ログイン